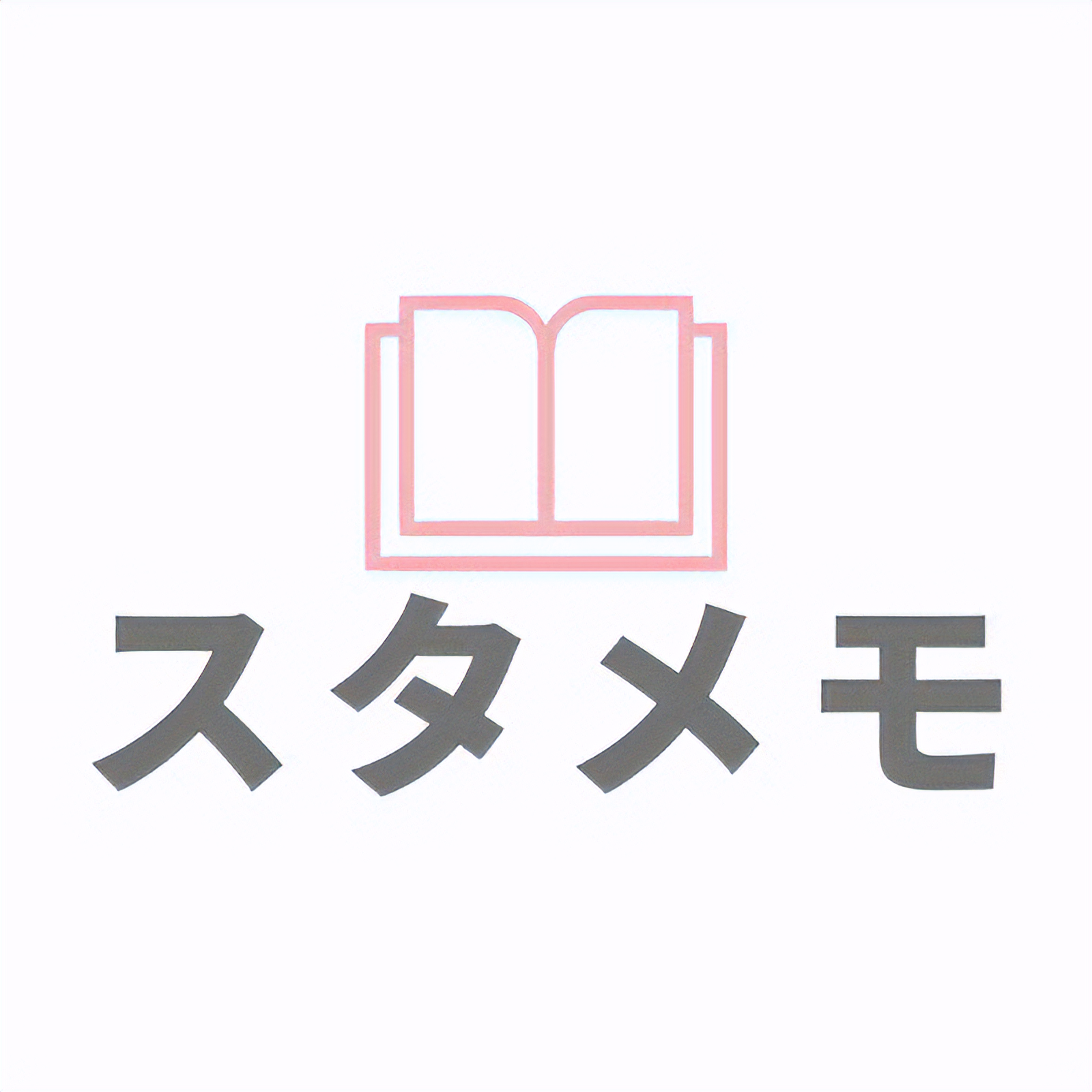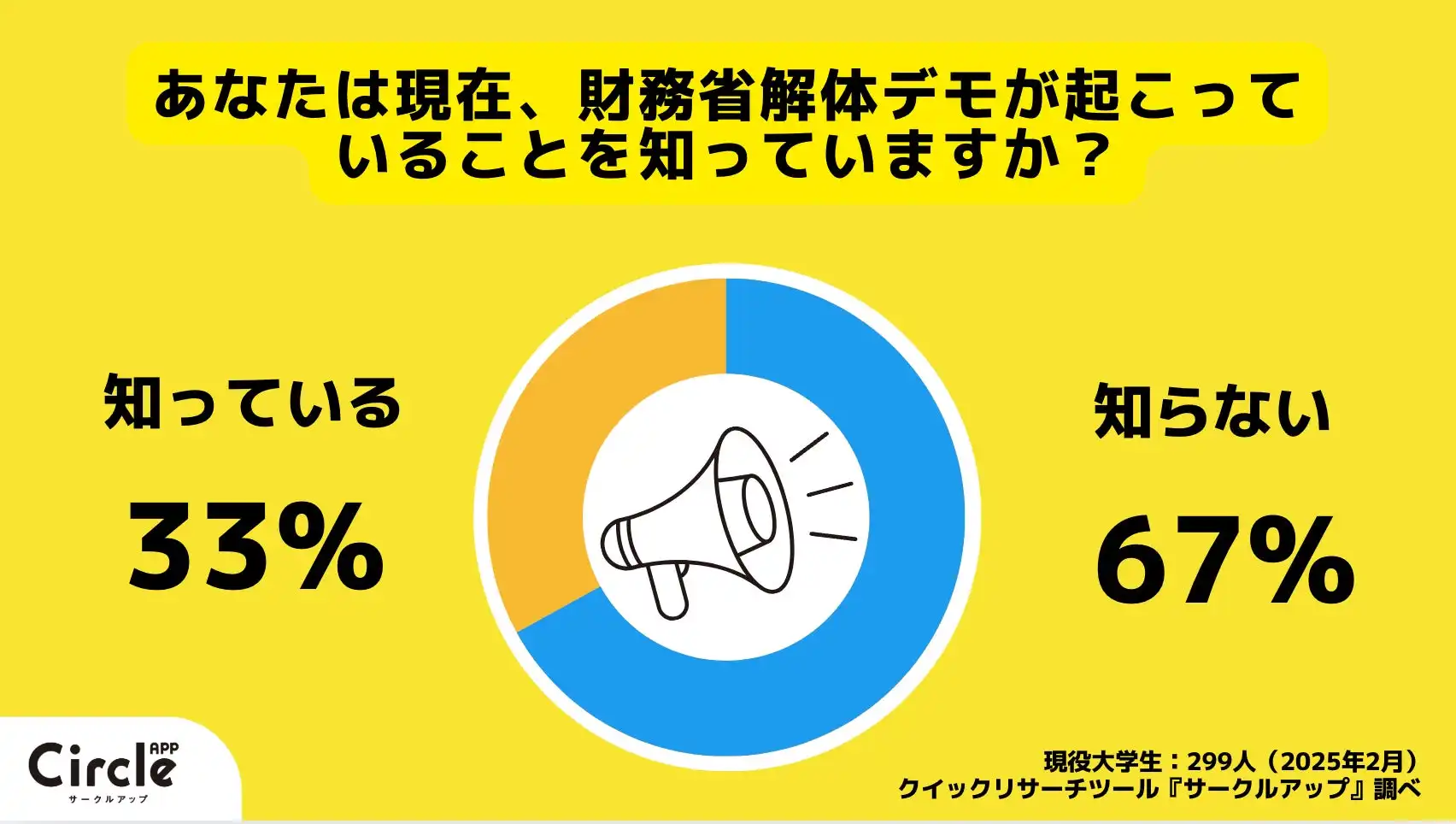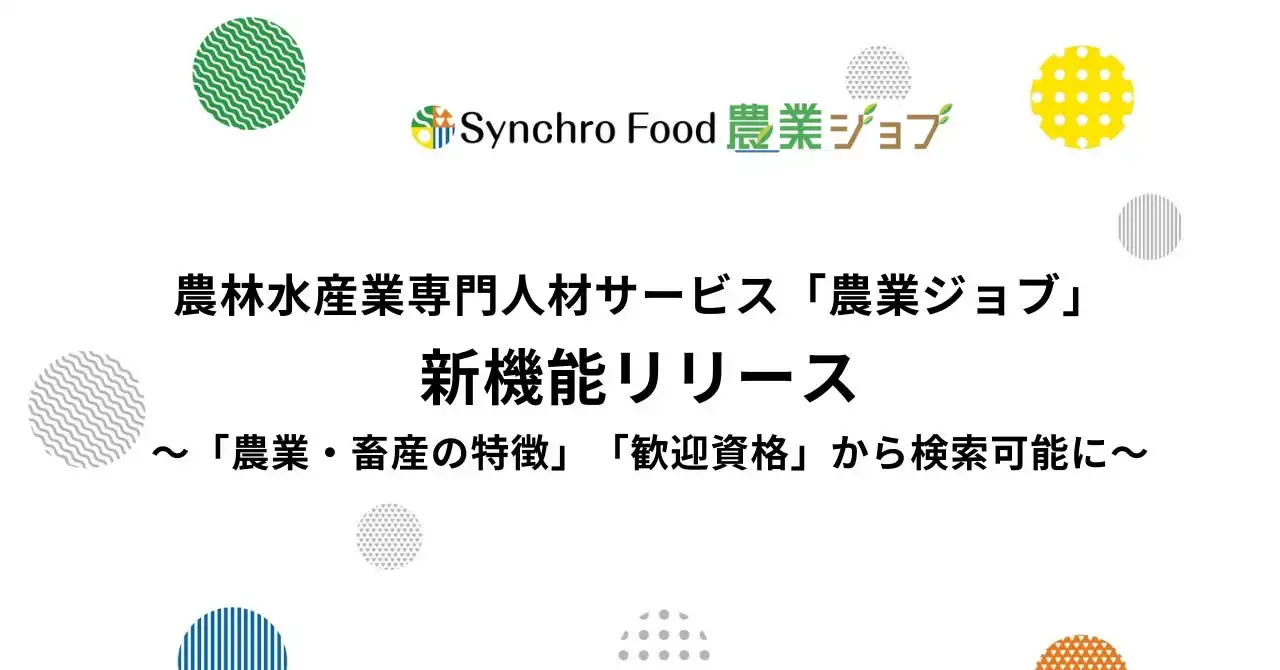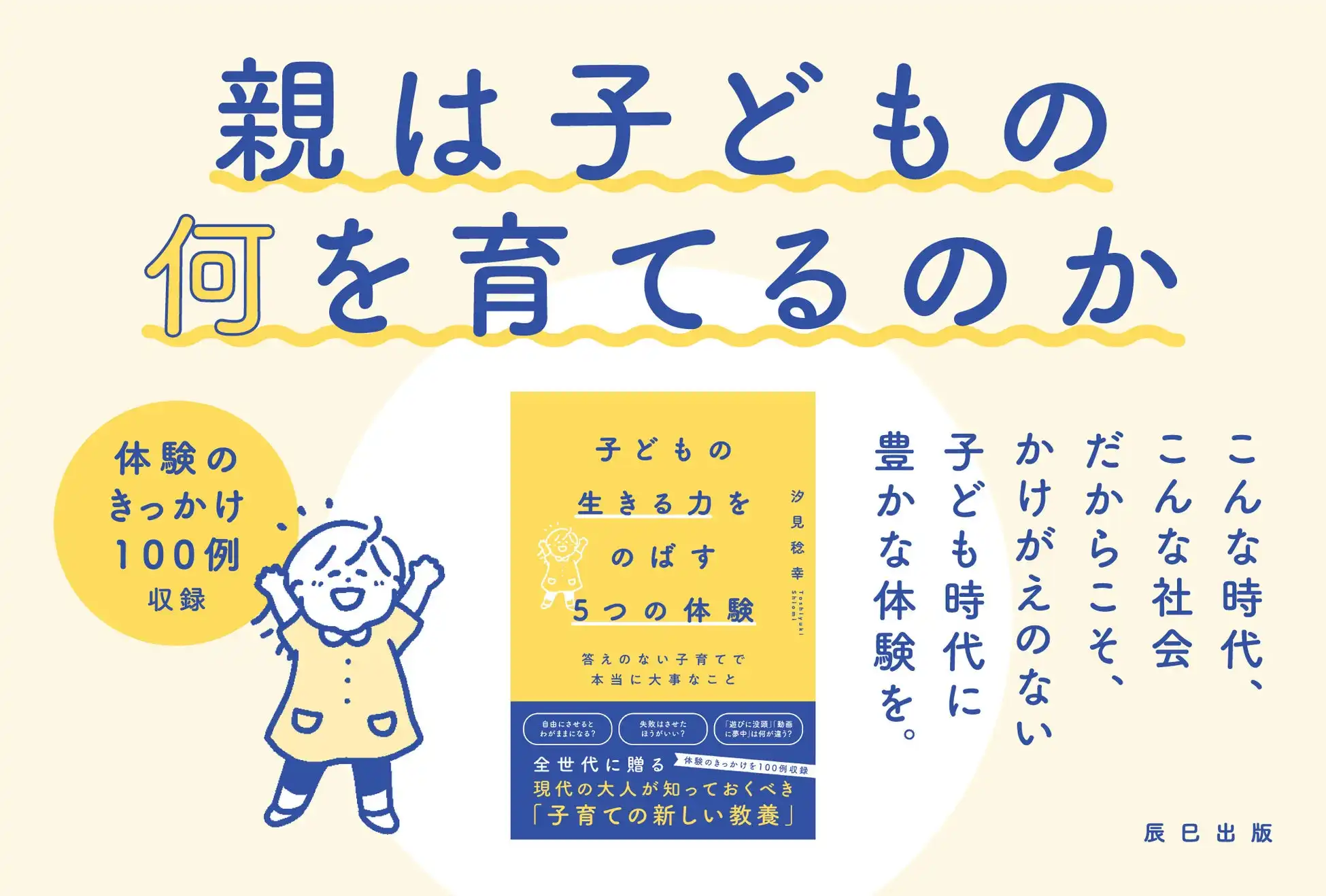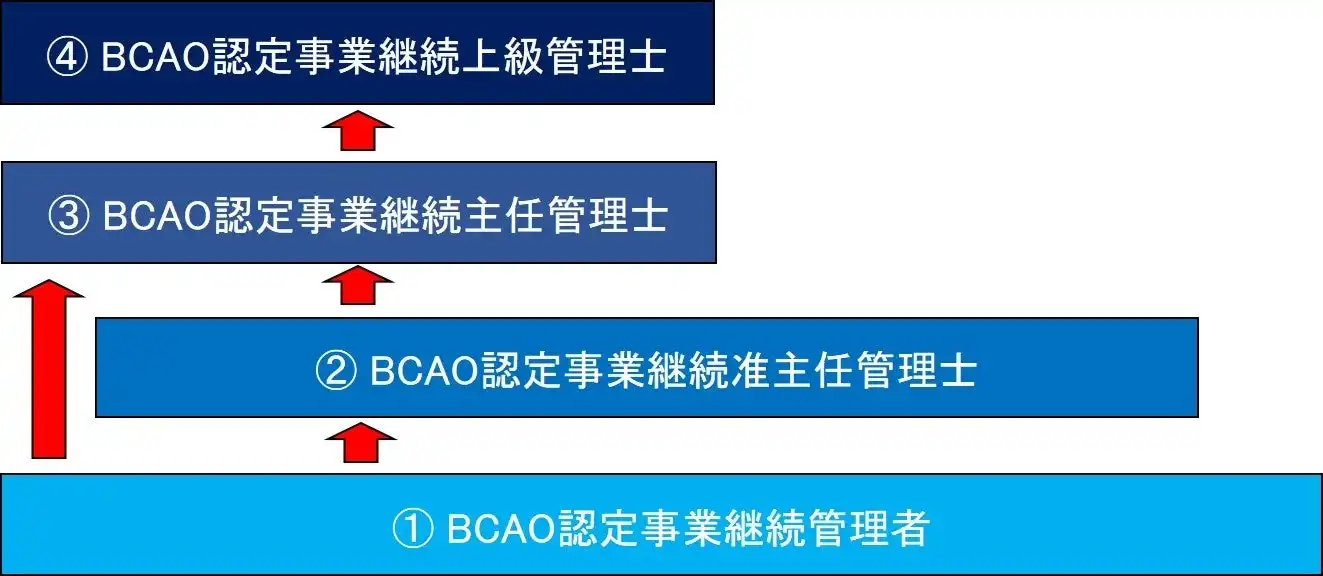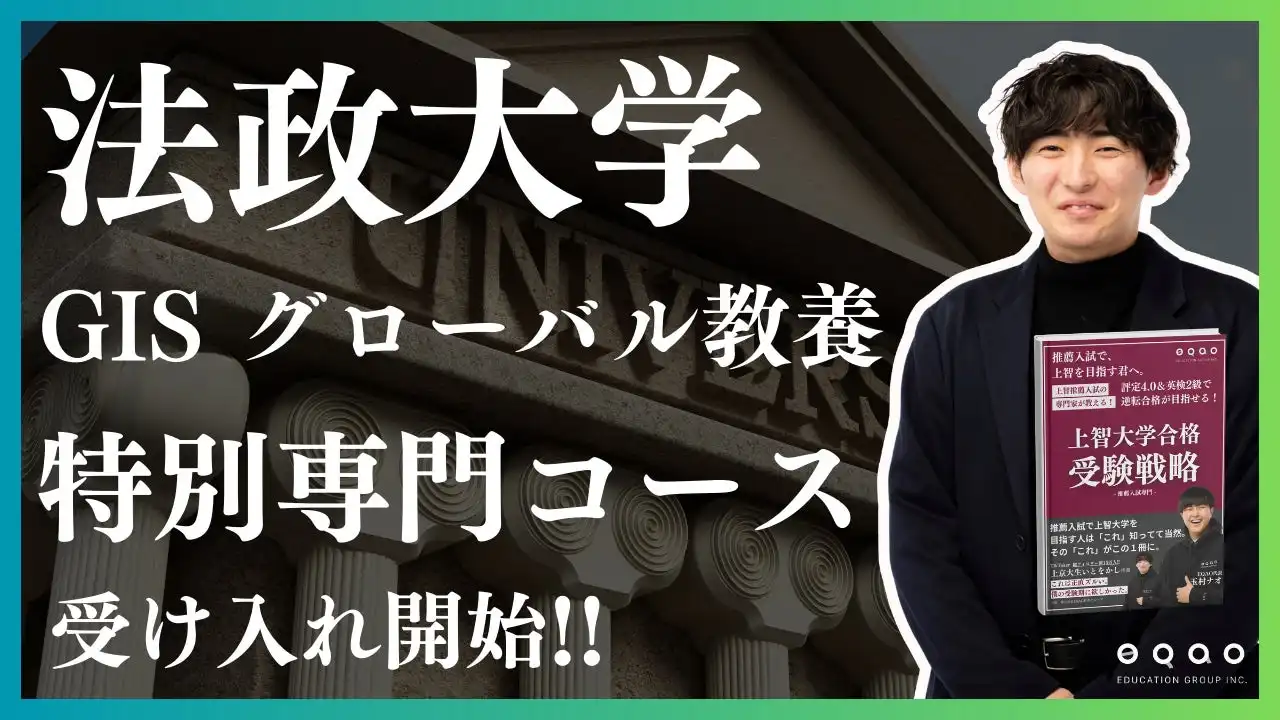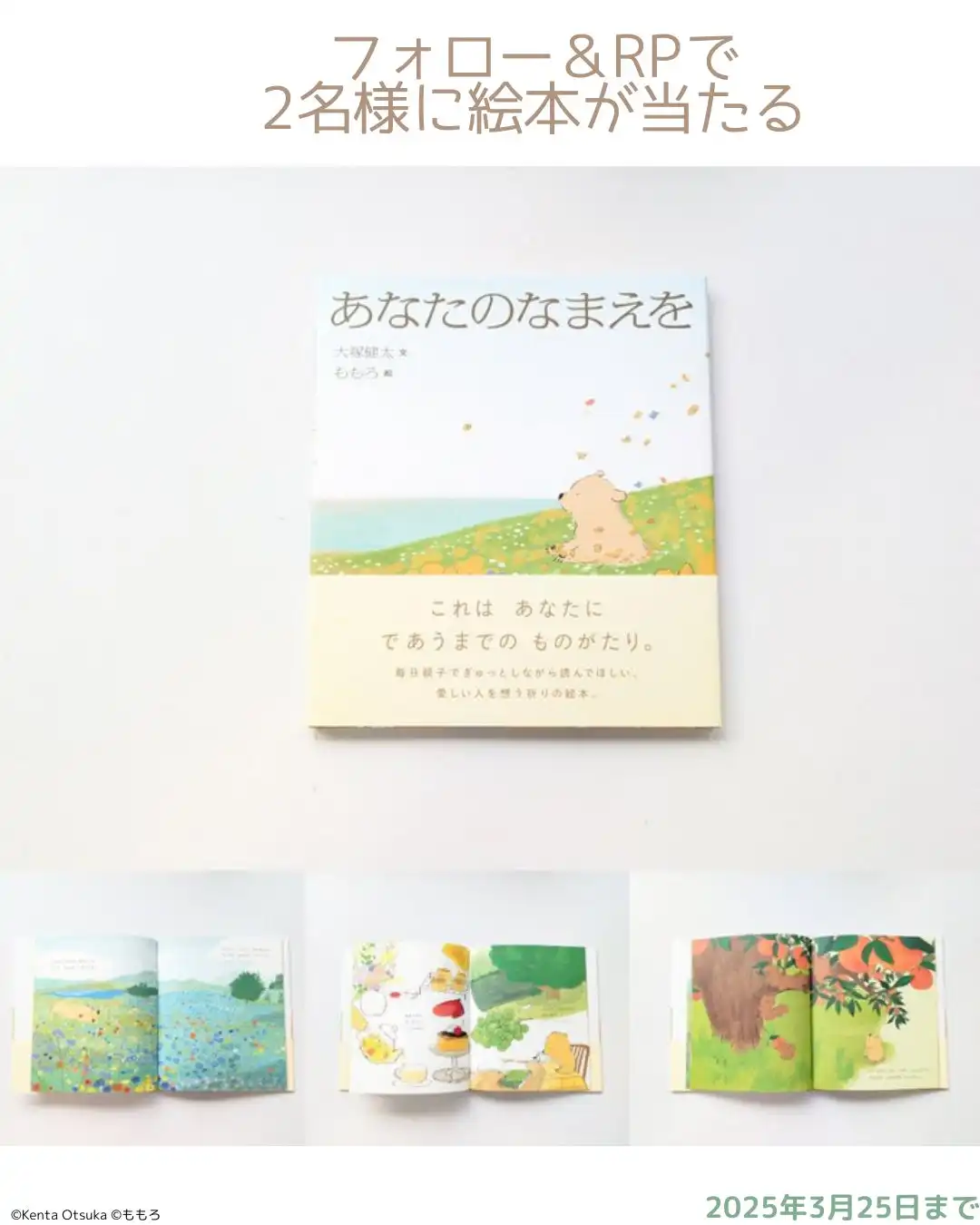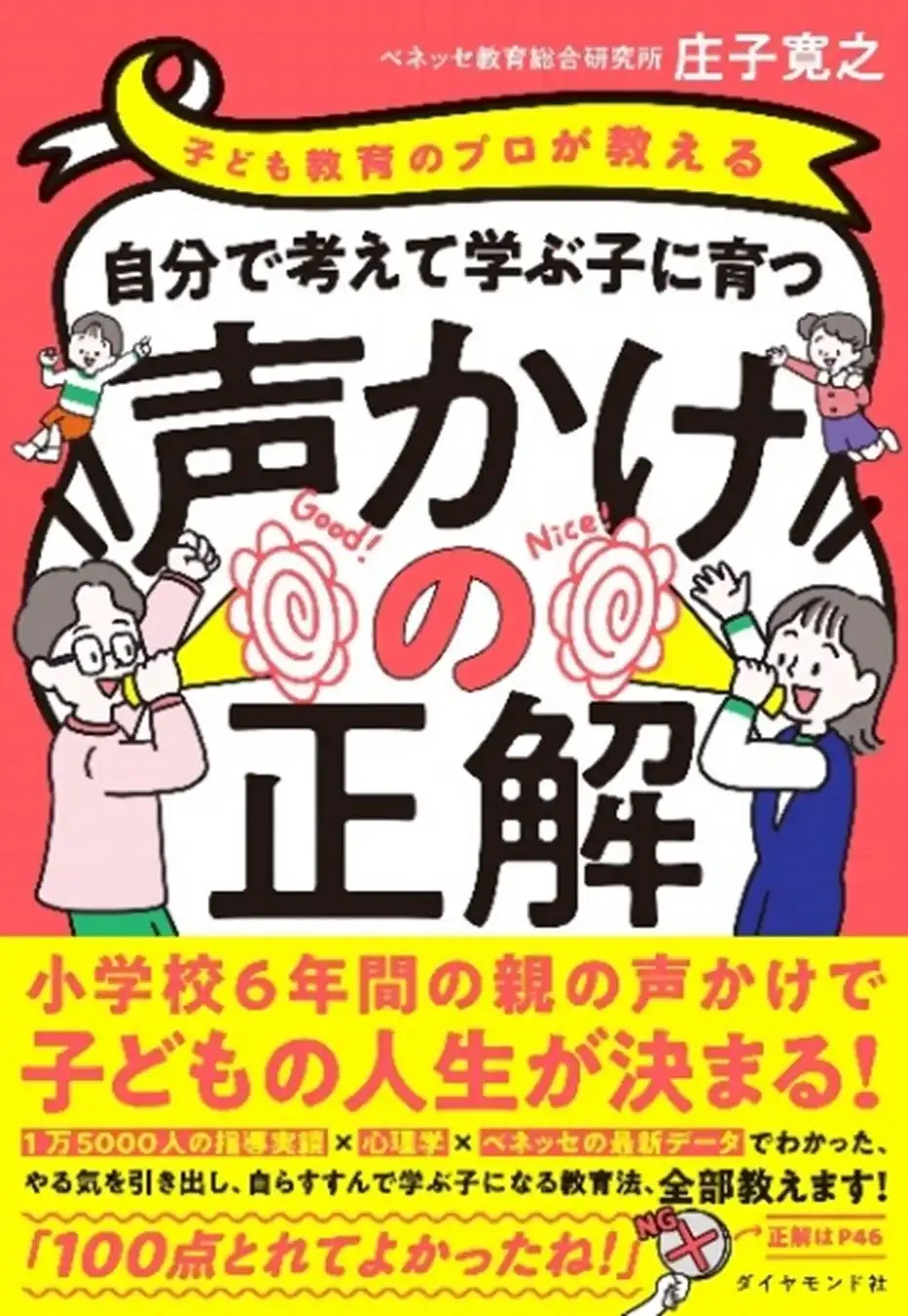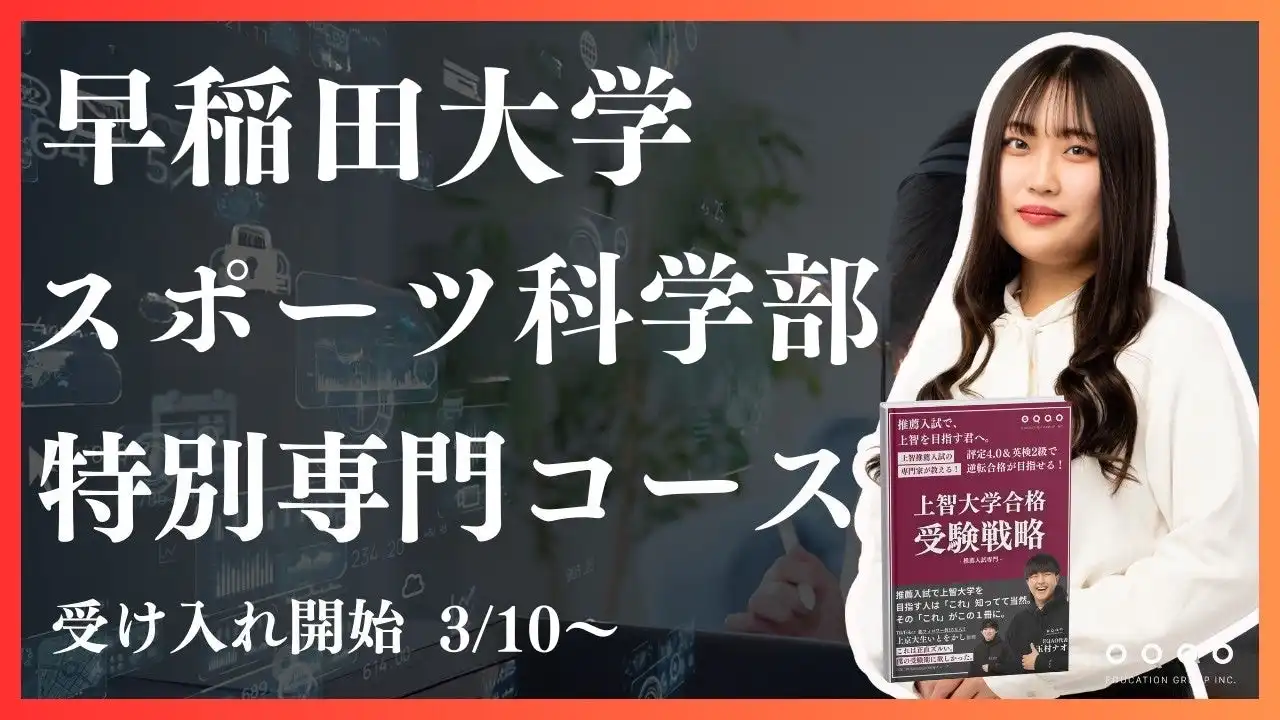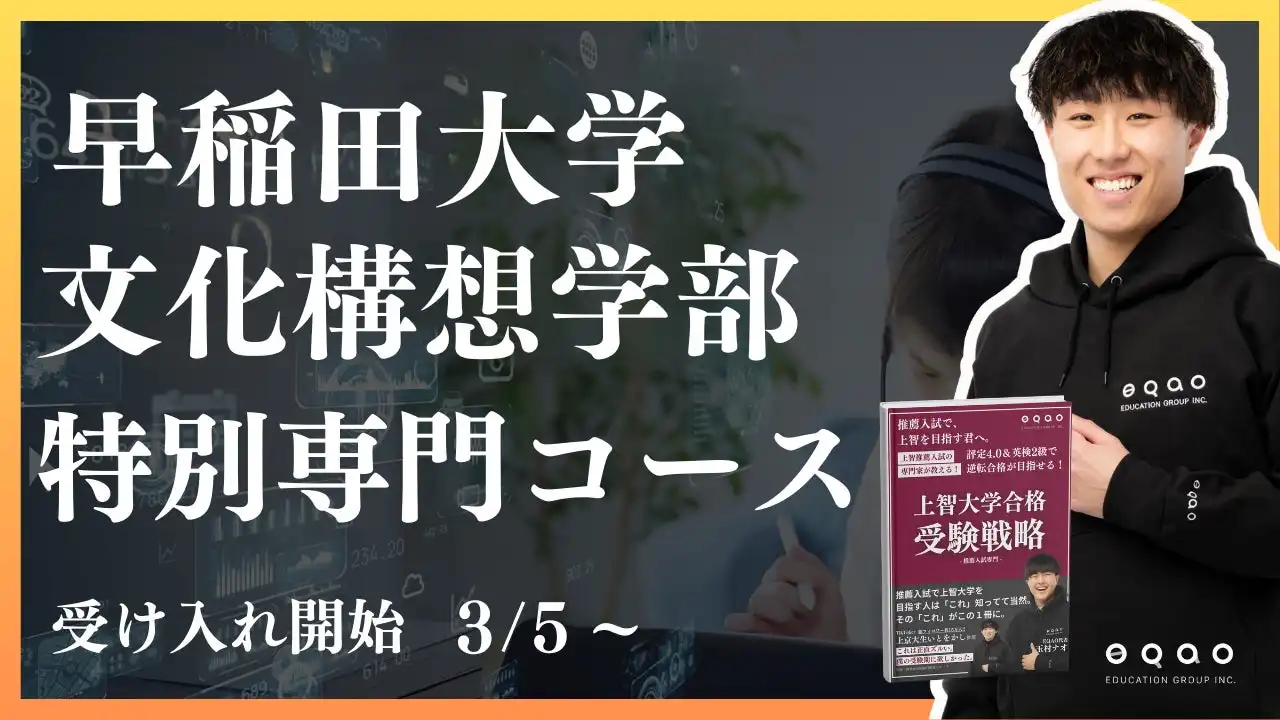シードと中央大学りこボラ!がYouTubeで理科実験教室を配信開始、光の散乱現象をペットボトルで再現し空の青さを解説
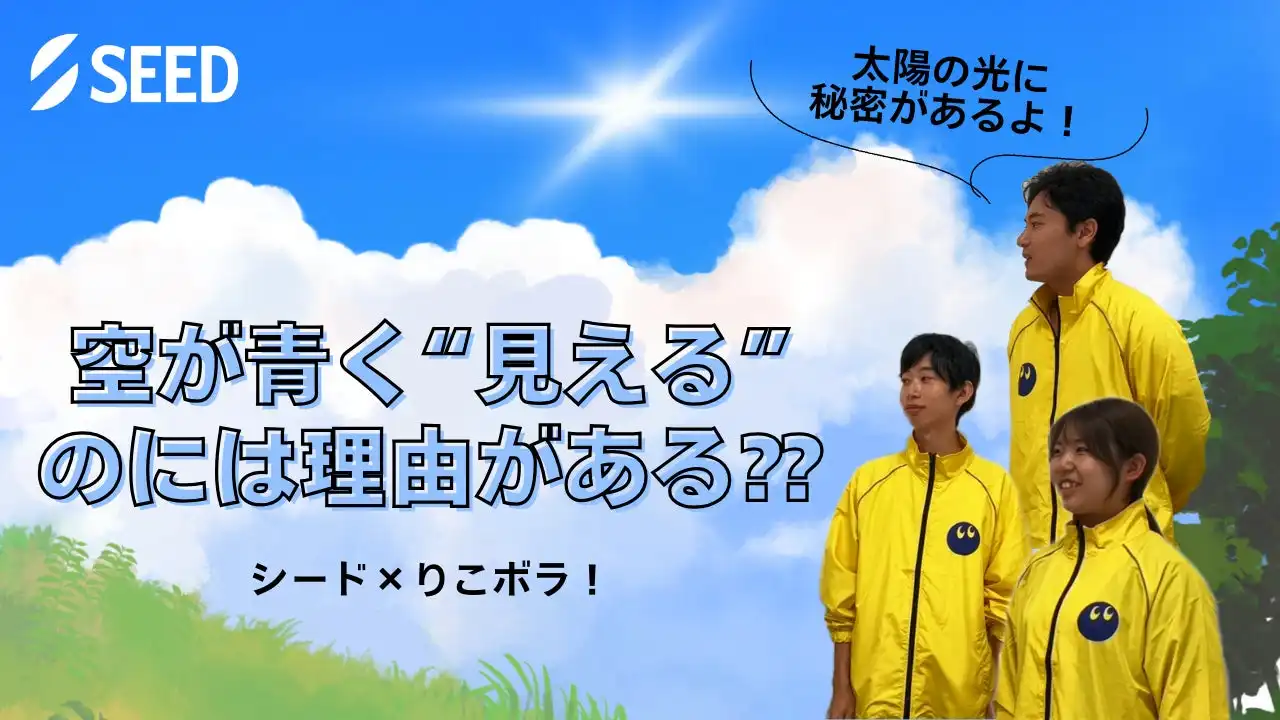
記事の要約
- シードと中央大学りこボラ!が理科実験教室を配信開始
- ペットボトルで空が青く見える原理を実験で解説
- YouTubeで子ども向け実験動画を2025年1月17日から公開
シードと中央大学の理科実験教室YouTubeコラボレーション
コンタクトレンズメーカーの株式会社シードは中央大学ボランティアセンター公認学生団体りこボラ!とタッグを組み、2025年1月17日からYouTubeで理科実験教室の配信を開始した。企画立案から両者で取り組んだこの試みは、理系の学生によるボランティア活動と企業の社会貢献活動が融合した新しい教育コンテンツとなっている。
実験内容は光の散乱現象に着目し、ペットボトル内で空が青く見える仕組みを再現する内容となっている。豆乳を使用した実験では、波長の短い青い光が散乱しやすい性質を利用し、地球の大気で起こる現象を分かりやすく説明する工夫が凝らされている。
この教育コンテンツは4分20秒の動画として公開され、低年齢層から理科への興味を引き出すことを目指している。家族で一緒に実験を楽しめる内容設計により、科学的思考の育成だけでなく、家族間のコミュニケーション促進にも貢献することが期待されている。
理科実験教室の概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 配信開始日 | 2025年1月17日 |
| 動画時間 | 4分20秒 |
| 実験テーマ | 空が青く見える原理の探究 |
| 使用材料 | ペットボトル、水、豆乳、ライト |
| 教育目的 | 理科実験の楽しさ体験、家族間コミュニケーション促進 |
光の散乱について
光の散乱とは、光が物質に当たって様々な方向に分散される現象のことを指す。主な特徴として、以下のような点が挙げられる。
- 波長の長さによって散乱のしやすさが異なる
- 青い光は波長が短く散乱しやすい性質がある
- 赤い光は波長が長く散乱しにくい特徴を持つ
ペットボトルを使用した実験では、豆乳の粒子に光を当てることで散乱現象を再現している。光の波長による散乱の違いを視覚的に確認できる実験であり、日常生活で目にする空の青さの原理を理解するための効果的な教材として活用されている。
理科実験教室の教育効果に関する考察
身近な材料を使用した実験を通じて複雑な自然現象を可視化することは、子どもたちの科学的思考力を育む上で極めて効果的な手法である。特にYouTubeという親しみやすいプラットフォームを活用することで、理科教育へのアクセシビリティが大幅に向上し、より多くの子どもたちが科学に触れる機会を得ることが可能となっている。
企業と大学生が連携して教育コンテンツを制作する取り組みは、実験の専門性と若い世代の視点を組み合わせた新しい教育モデルとなり得る。実験の原理説明に加えて、家族でのコミュニケーションを促進する要素を含めることで、科学教育と情操教育の両面からアプローチできる可能性を持っている。
継続的なコンテンツ制作と配信により、理科実験の動画ライブラリが充実することで、学校教育を補完する教材としての活用も期待できる。教育現場のニーズに応じた実験テーマの選定や、年齢層に合わせた説明方法の工夫など、さらなる発展の可能性を秘めている。
参考サイト/関連サイト
- PR TIMES.「コンタクトレンズのシード×中央大学ボランティアセンター公認活動団体 りこボラ! 子ども向け理科実験教室「空が青く見えるのはどうして?」1月17日(金)YouTubeにて配信スタート | 株式会社シードのプレスリリース」.https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000038735.html, (参照 2025-01-18).