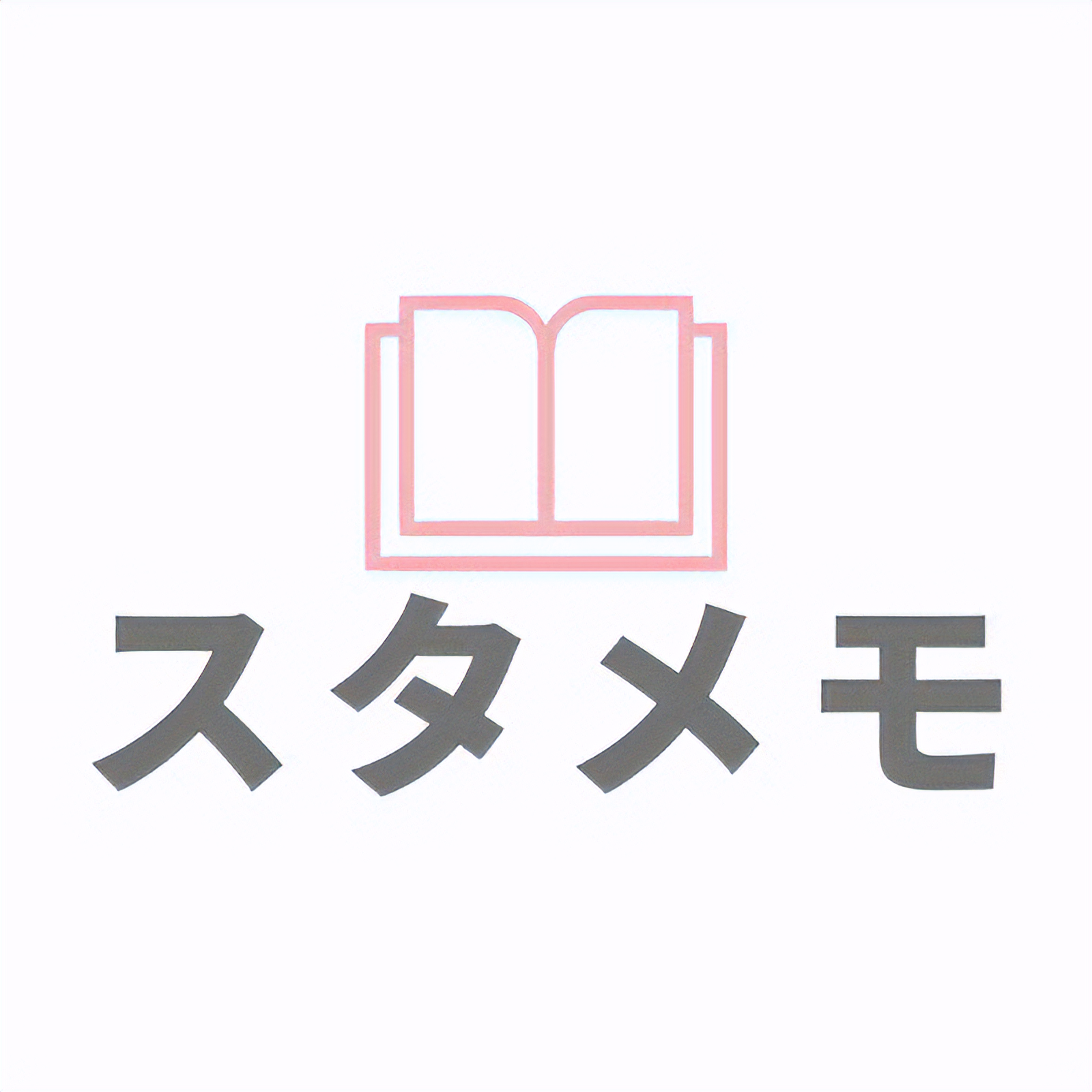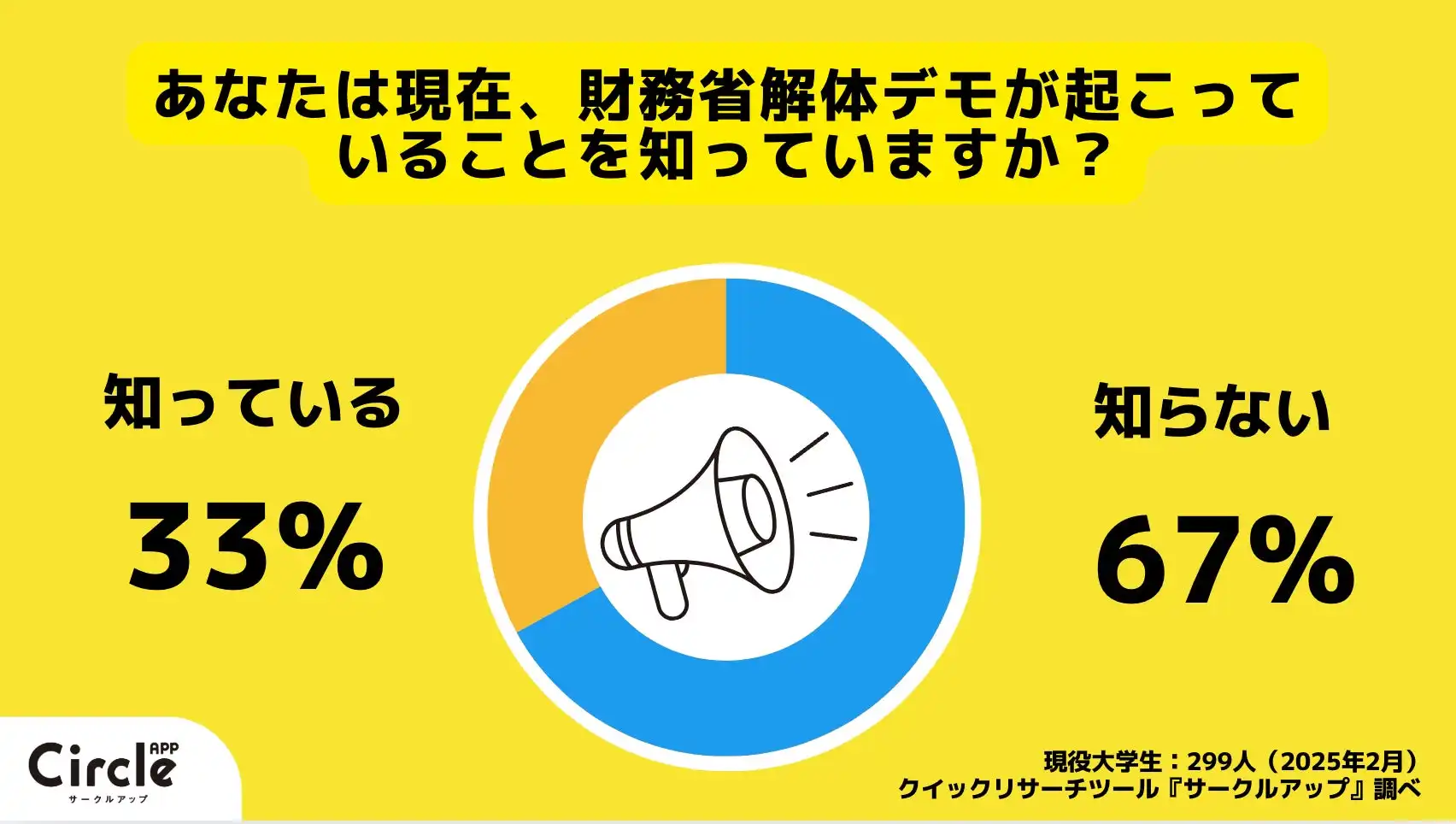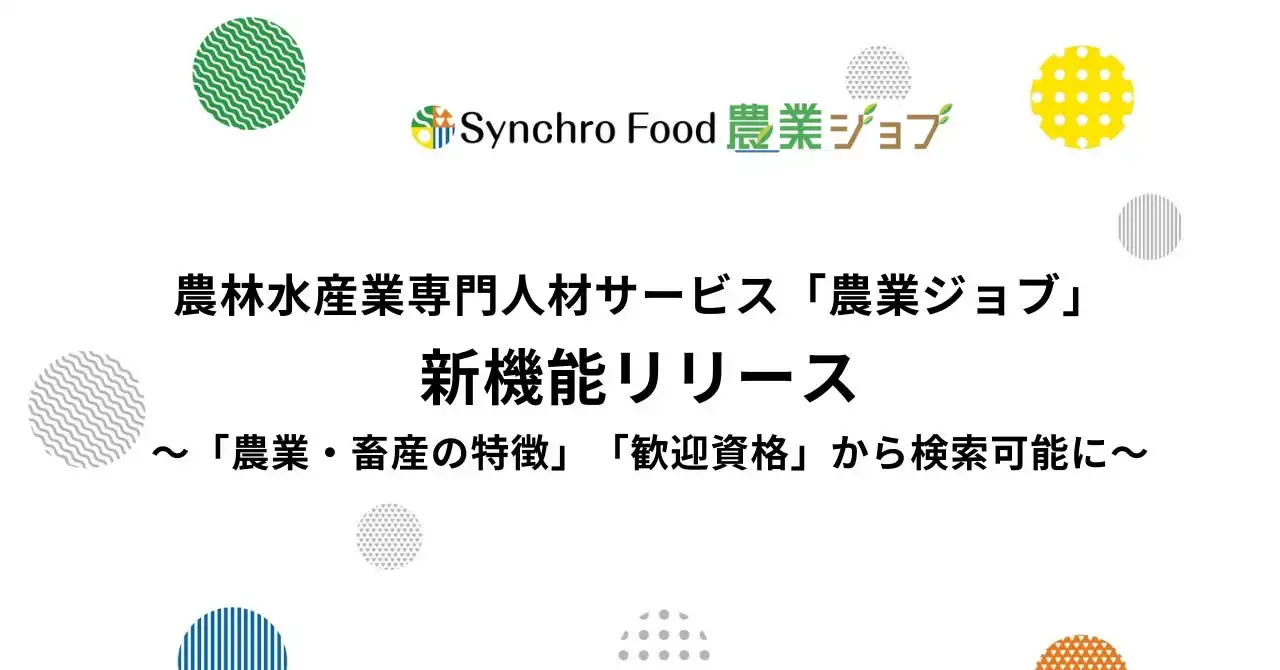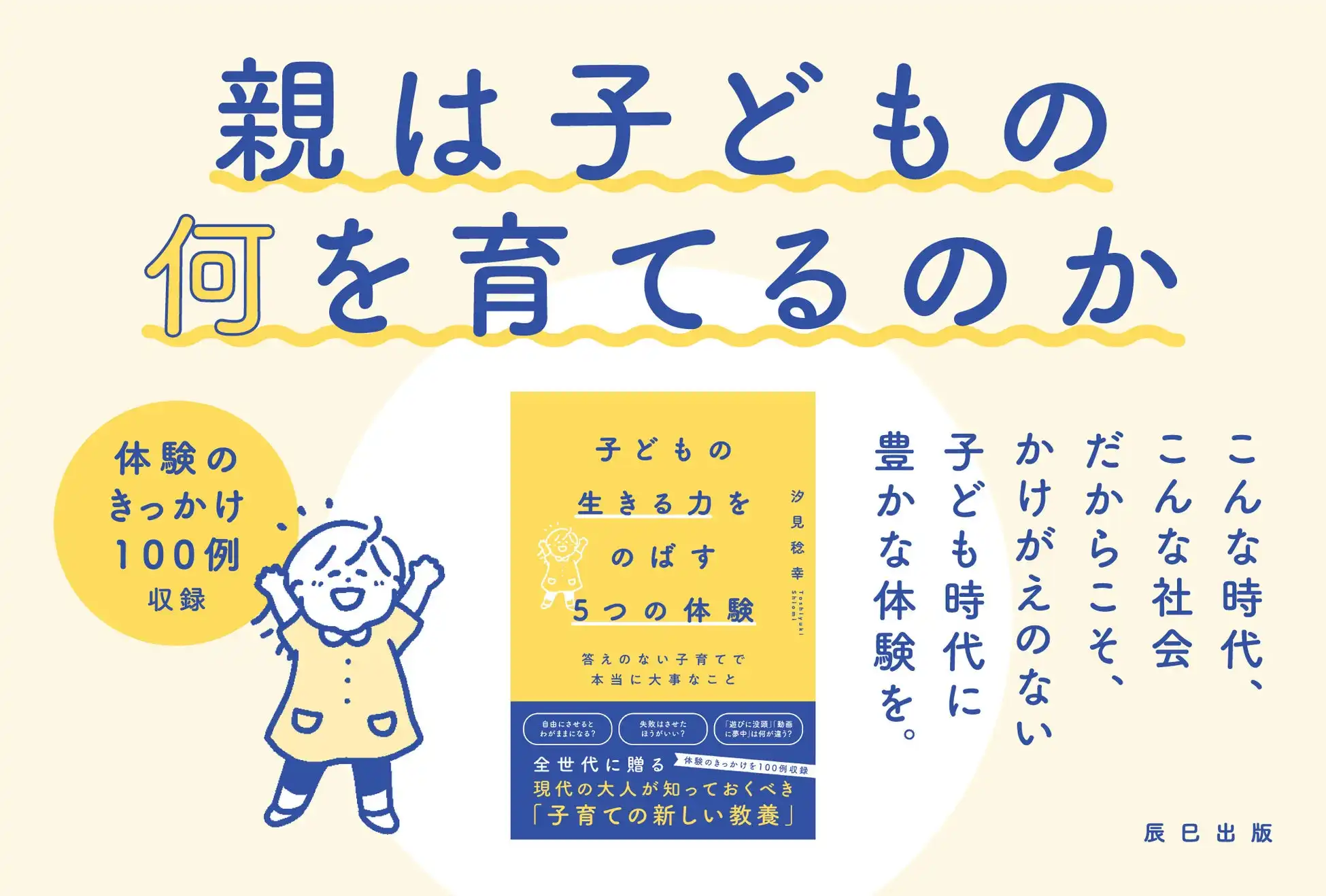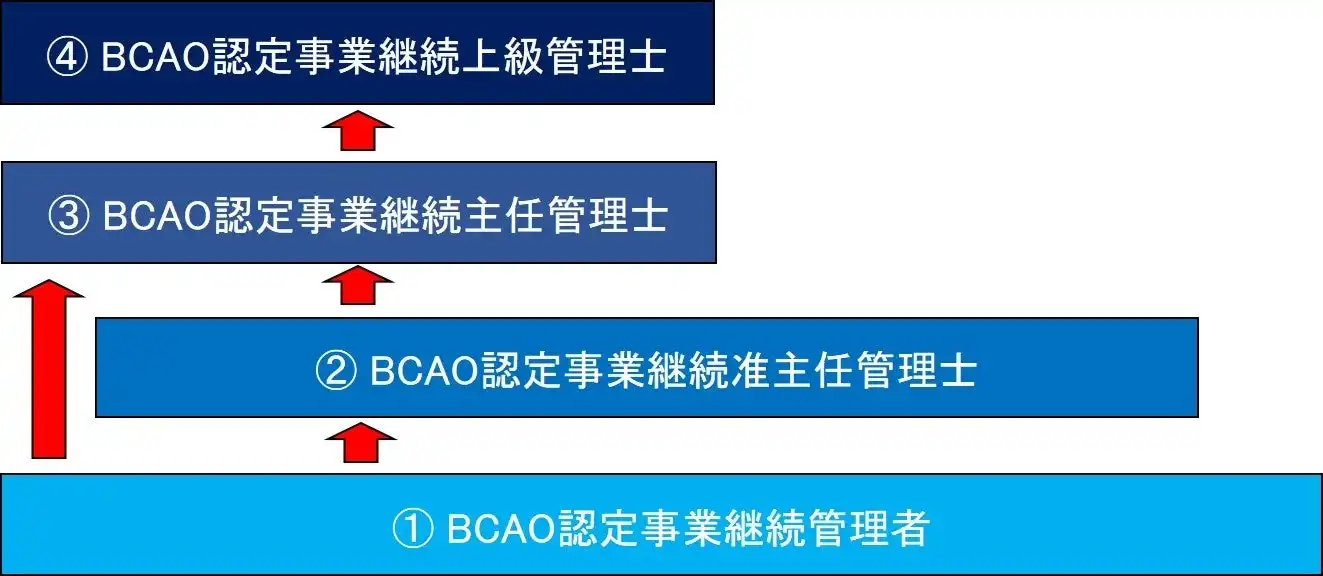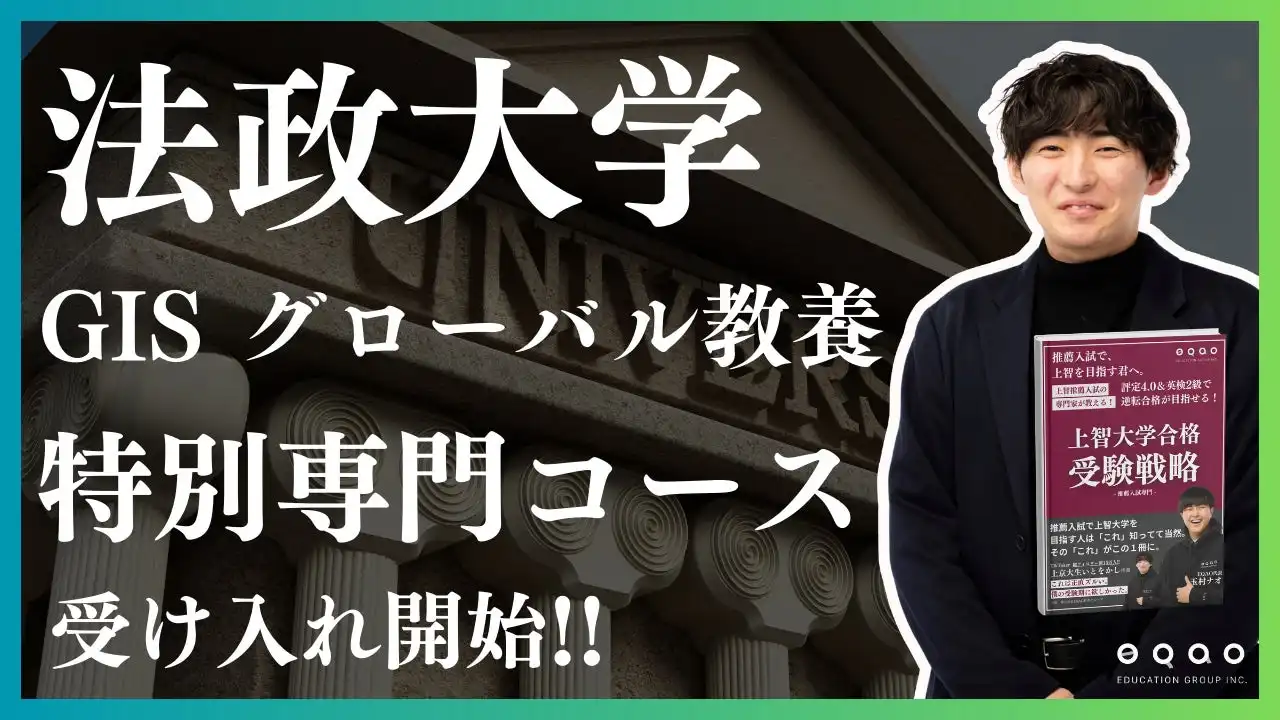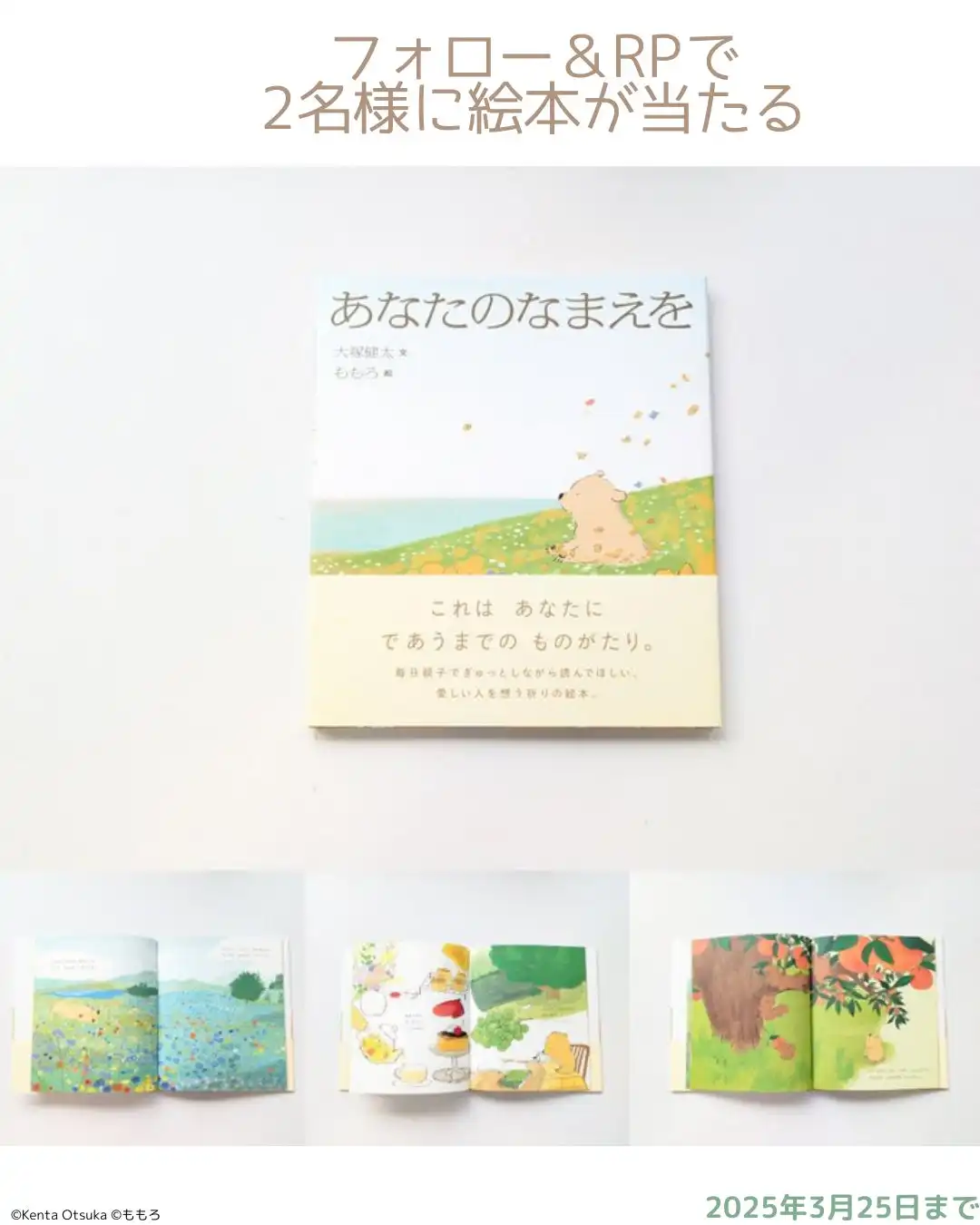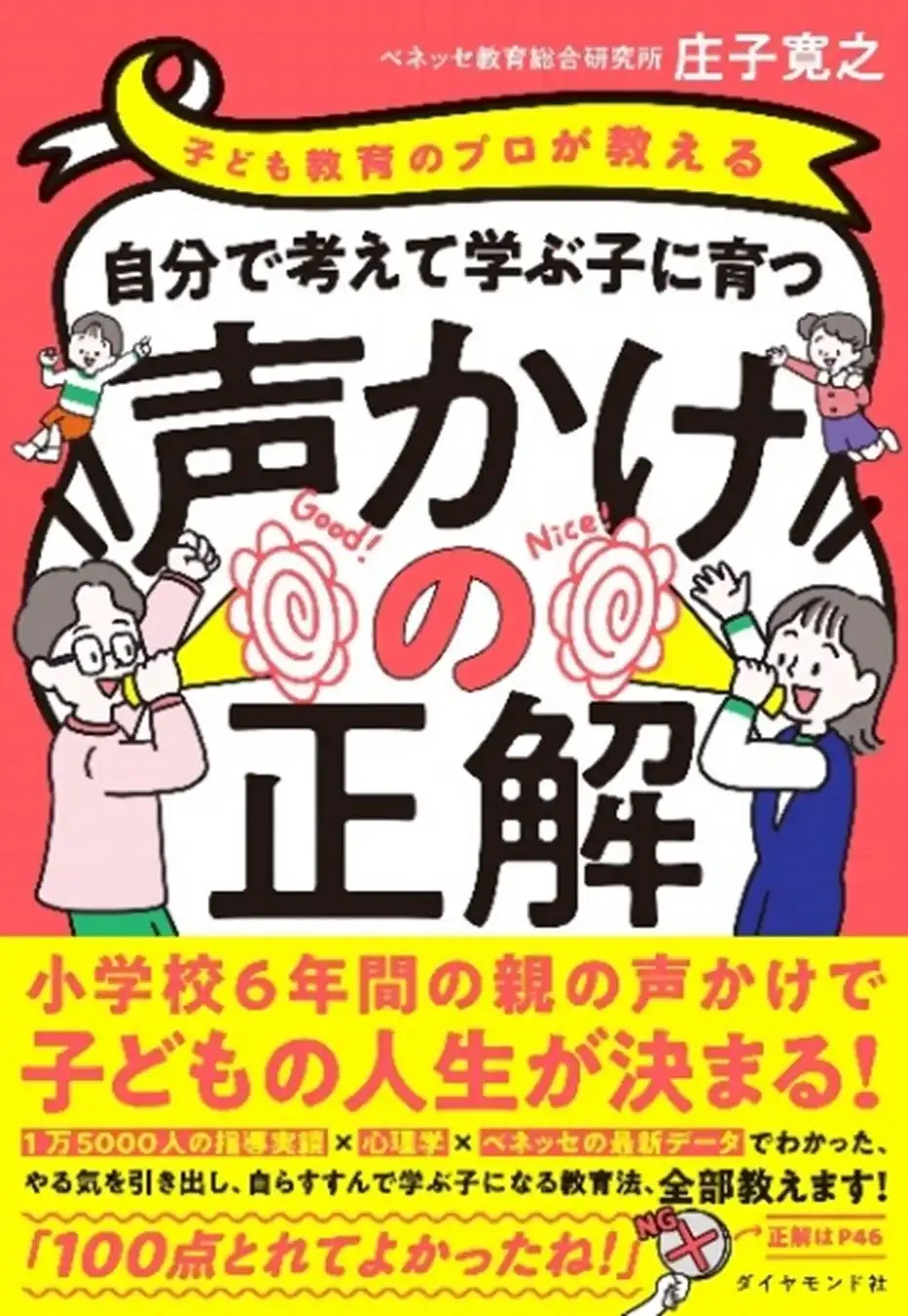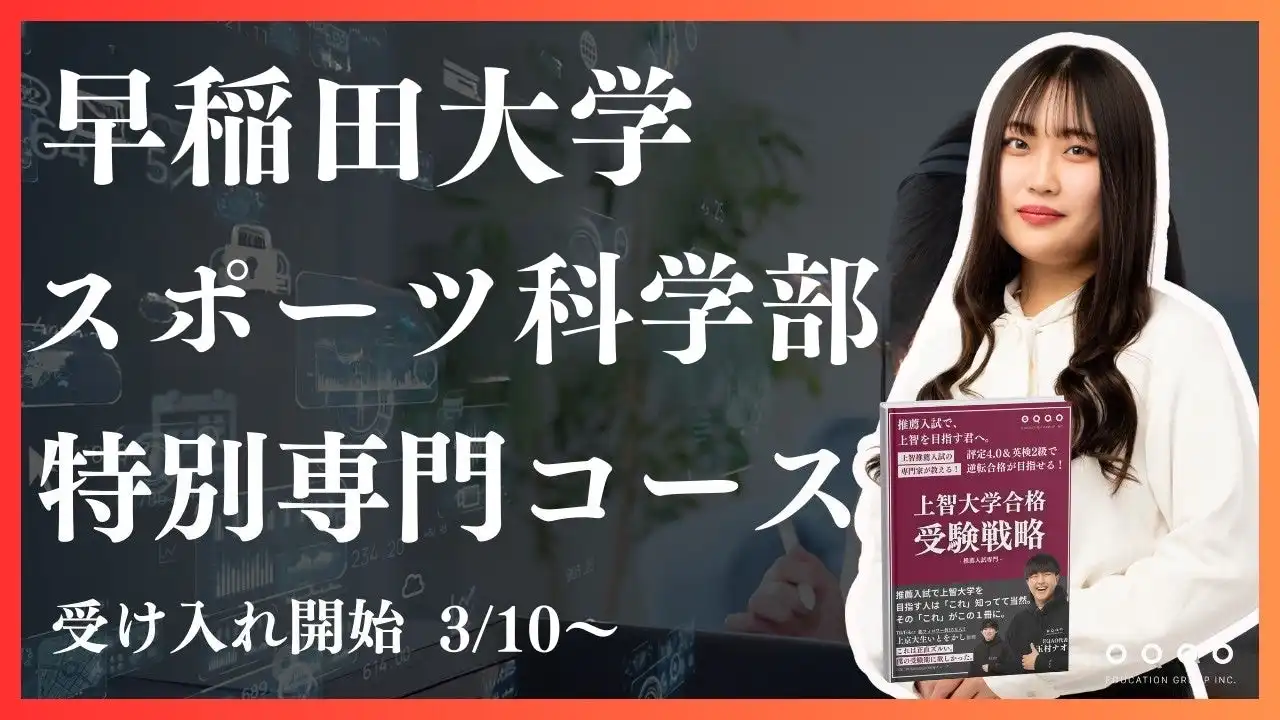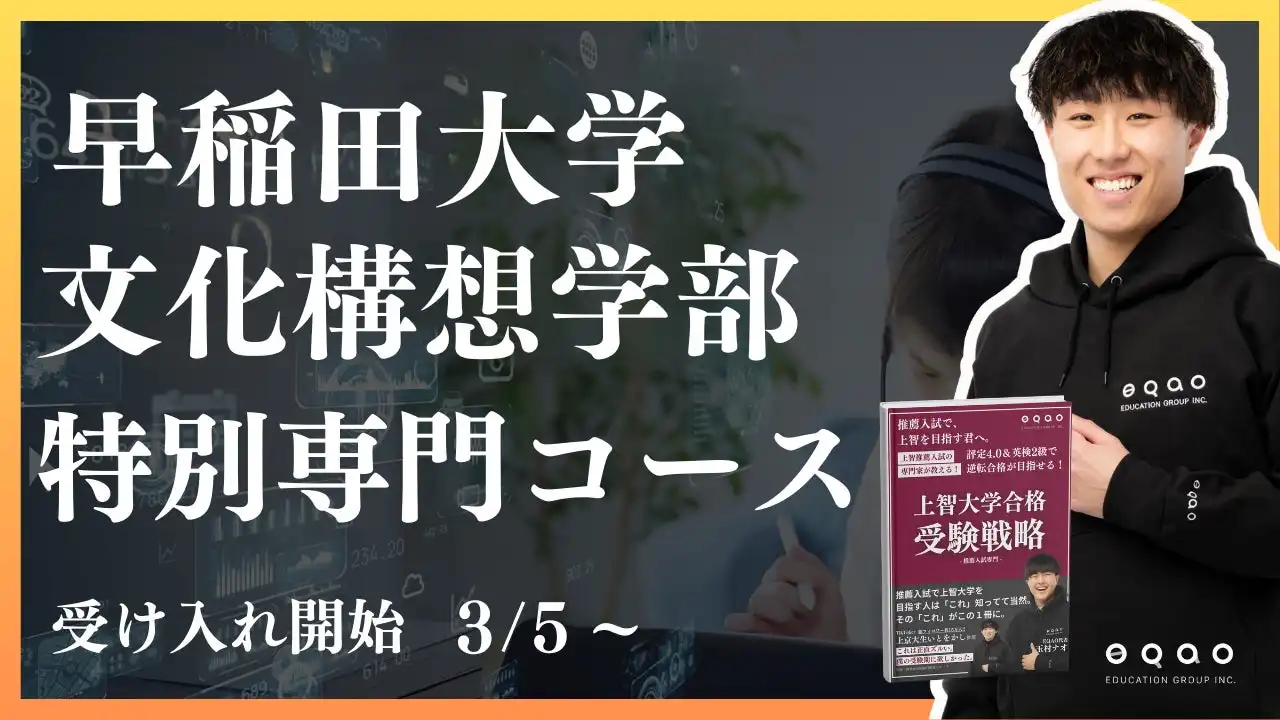日本身体障害者補助犬学会が第16回学術大会を開催、次世代の補助犬について多角的な議論が展開

記事の要約
- 日本身体障害者補助犬学会が第16回学術大会を開催
- 次世代の補助犬について様々な発表や講演を実施
- ほじょ犬のひろばとコラボレーションしデモンストレーションを実施
日本身体障害者補助犬学会第16回学術大会の開催概要
日本身体障害者補助犬学会は2025年1月11日から12日にかけて、四条畷学園短期大学にて第16回学術大会を開催した。学術大会では「次世代の補助犬について考える~人と犬との相互作用の構築に向けて~」をテーマに掲げ、日本介助犬協会から2名の職員が一般演題発表を行い、補助犬同伴受け入れに関する調査結果や独自のパピー育成プログラムについて詳細な報告を実施した。
学術大会では日本介助犬協会理事長の高柳氏が座長を務めるペット防災に関する教育講演や海外の取り組みを学ぶ国際シンポジウムなど、幅広いプログラムが展開された。さらに大阪府大東市のもりねき広場では補助犬3種類のデモンストレーションや各補助犬育成団体によるブース出展、クイズラリーなども行われ、多くの市民の参加を得て盛況な大会となった。
学術大会の特徴として、今年は初めて「ほじょ犬のひろば」とのコラボレーションを実現し市民参加型のイベントを展開した点が挙げられる。学会では補助犬がどのように当事者や社会に必要とされ、その効果を十分に発揮できるかについて、参加者が改めて考える機会を提供することに成功している。
補助犬学会第16回学術大会の開催内容
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 開催日時 | 2025年1月11日〜12日 |
| 開催場所 | 四条畷学園短期大学(大阪府大東市) |
| 主催 | 一般社団法人 日本身体障害者補助犬学会 |
| テーマ | 次世代の補助犬について考える~人と犬との相互作用の構築に向けて~ |
| 主な内容 | シンポジウム、演題発表、教育講演、補助犬デモンストレーション |
| 特別企画 | ほじょ犬のひろば(もりねき広場)でのイベント開催 |
介助犬について
介助犬とは、手や足に障がいのある人の日常生活を支援するために特別な訓練を受けた犬のことを指す。主な特徴として、以下のような点が挙げられる。
- 落とした物の拾い上げや携帯電話を持ってくるなどの作業が可能
- ドアの開閉など日常生活の基本動作をサポート
- 2024年9月末時点で全国60頭が活動中
介助犬の需要と供給には大きな開きがあり、2024年9月末時点で全国で活動している介助犬は60頭に留まっている。一方で介助犬を必要としている人は15,000人ほどいると推定されており、介助犬の育成と普及が大きな課題となっている。
補助犬学術大会に関する考察
日本身体障害者補助犬学会第16回学術大会での様々な発表や講演は、補助犬の育成や活用における課題解決に向けた重要な一歩となっている。特に日本介助犬協会のパピー育成プログラムに関する発表は、介助犬の質的向上と頭数の確保という二つの課題に対する具体的な取り組みを示すものであり、今後の発展が期待できる内容だ。
補助犬の社会的認知度向上と受け入れ体制の整備は依然として大きな課題として存在している。特に介助犬に関しては必要とする人数に対して実働頭数が著しく少ないという現状があり、育成体制の強化と同時に、社会全体での理解促進と受け入れ環境の整備が不可欠となっている。
今回の学術大会で実施された市民参加型イベントは、補助犬に関する理解促進において効果的なアプローチとなった。今後は研究者や専門家による学術的な議論に加え、一般市民との交流機会を増やし、補助犬の社会的価値と必要性について広く認知を深めていく取り組みが重要になるだろう。
参考サイト/関連サイト
- PR TIMES.「【次世代の補助犬について考える】日本身体障害者補助犬学会 第16回学術大会が大阪府で開催 | 社会福祉法人 日本介助犬協会のプレスリリース」.https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000196.000058195.html, (参照 2025-01-22).