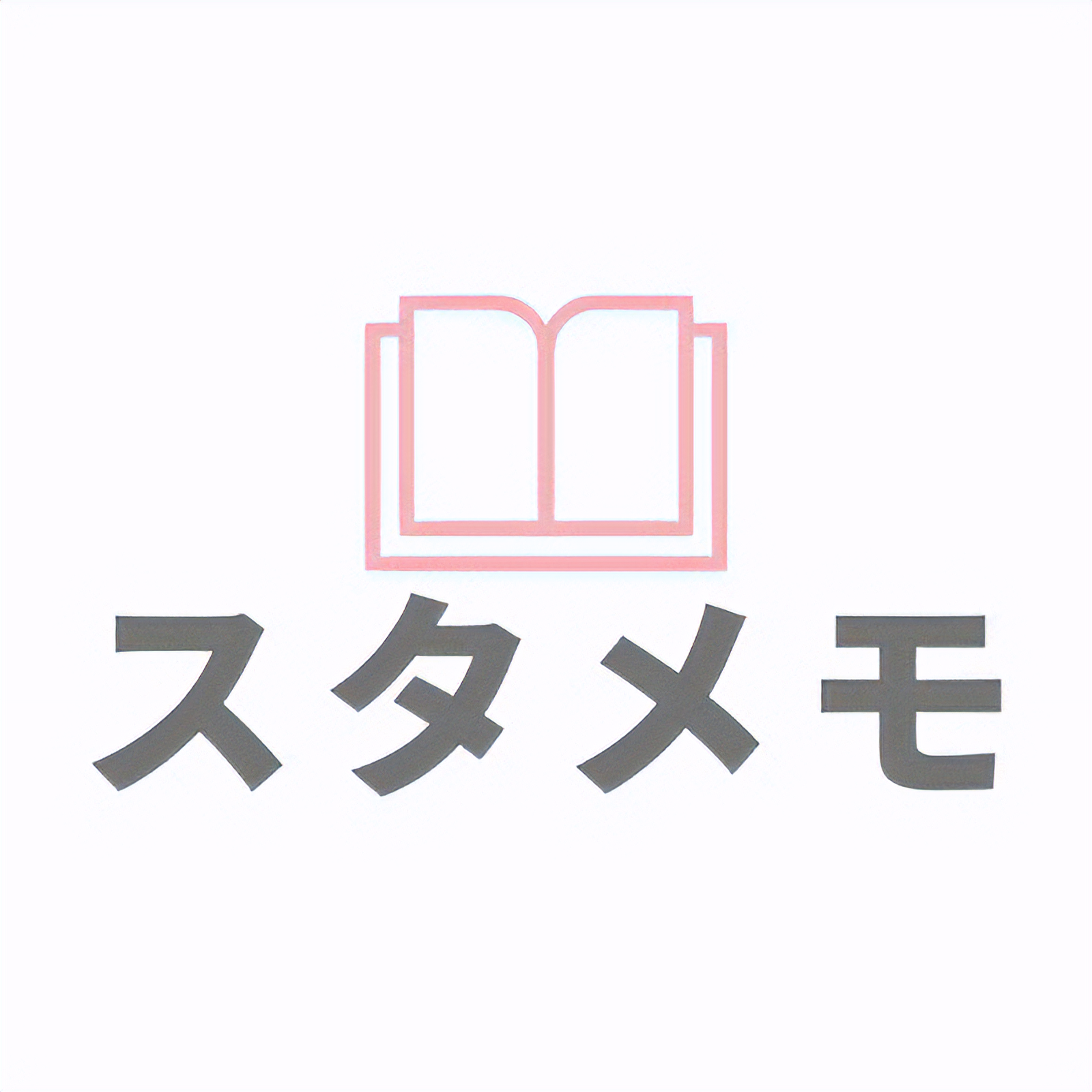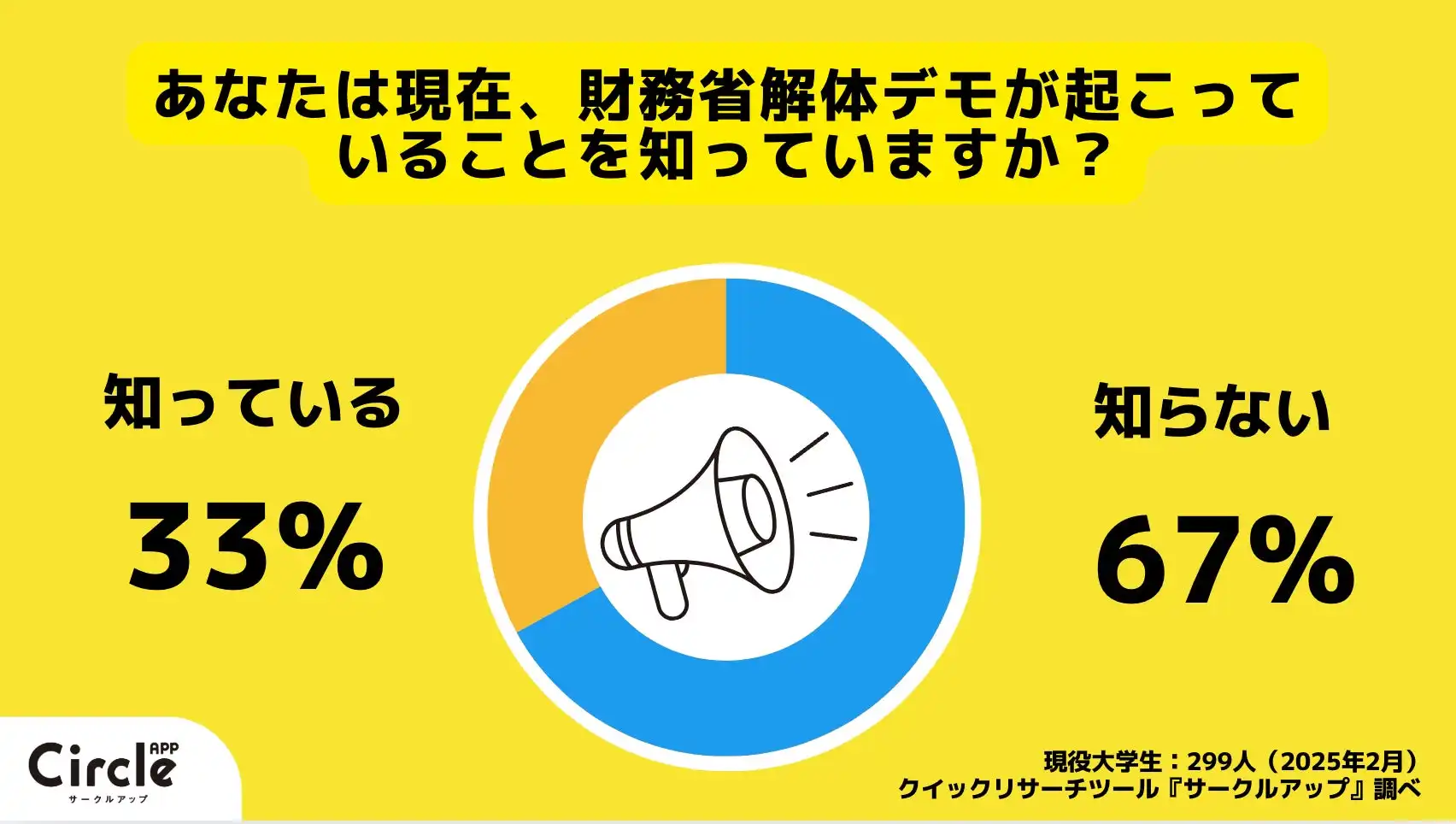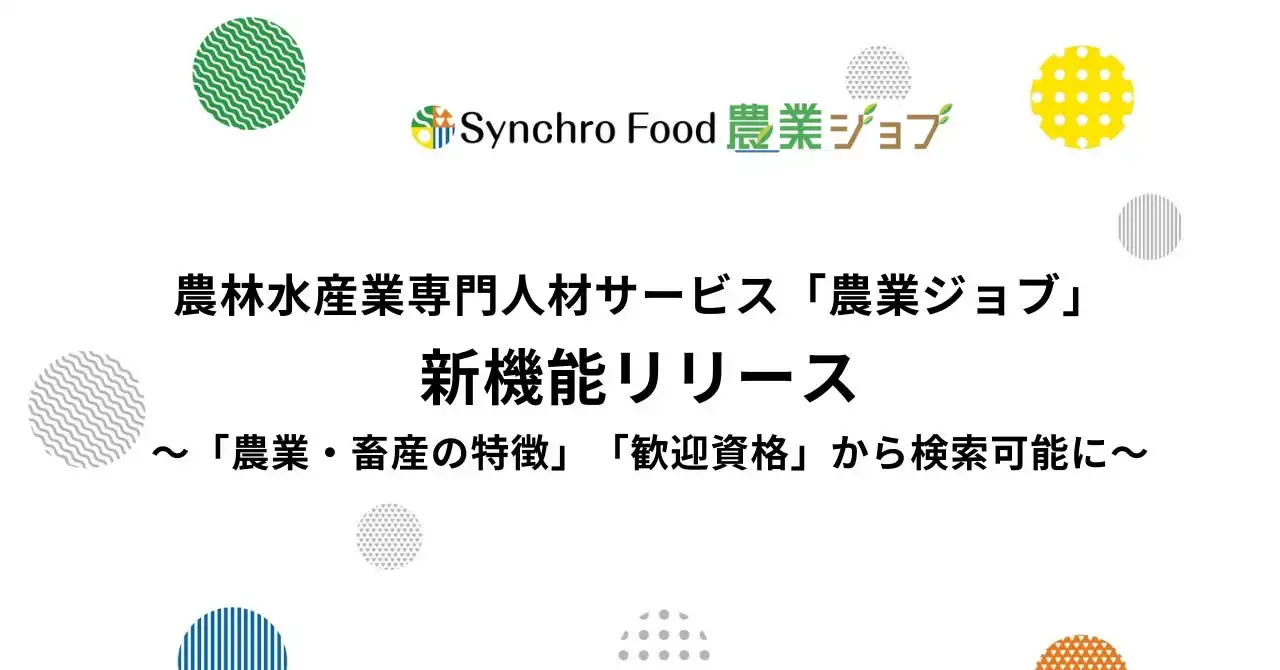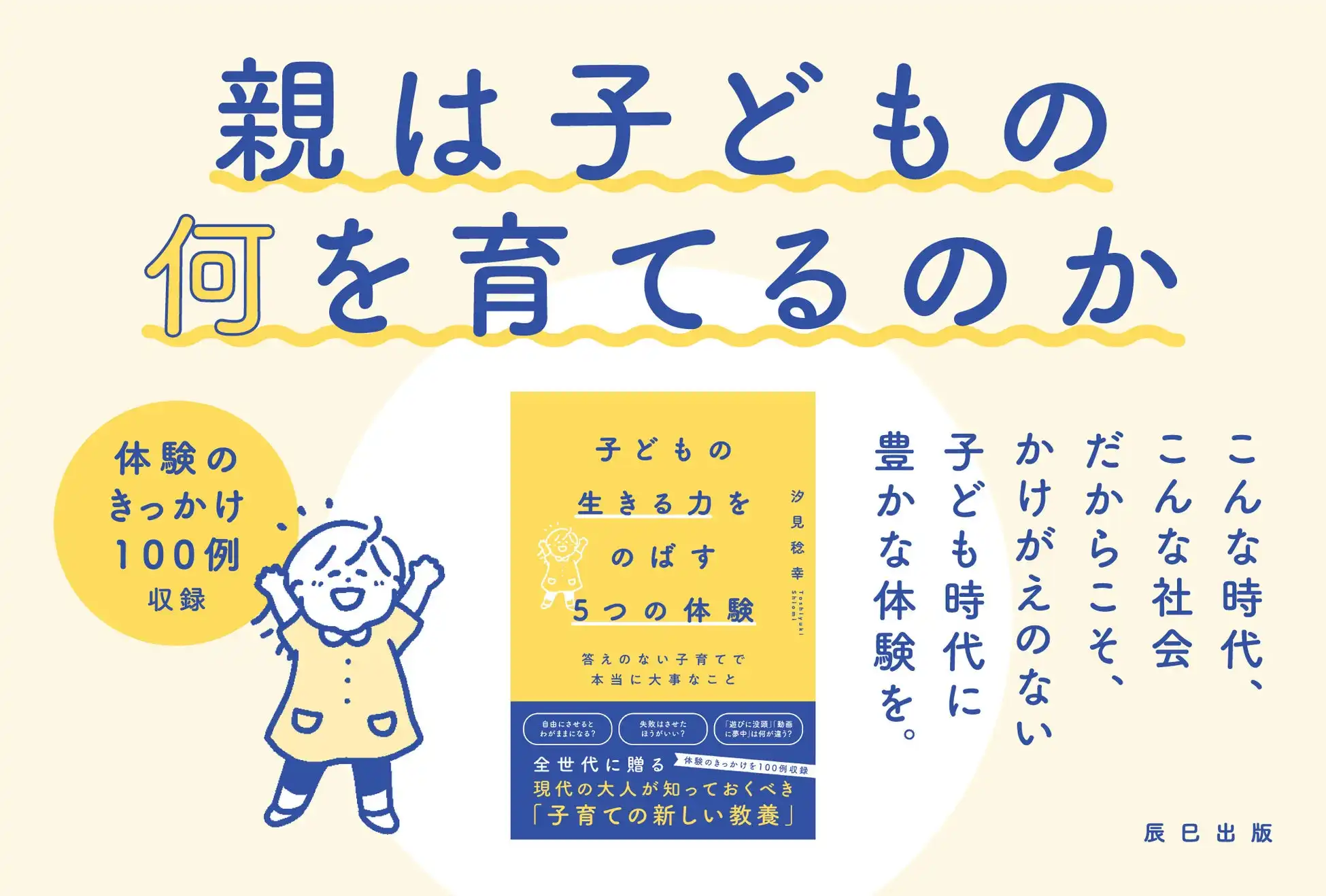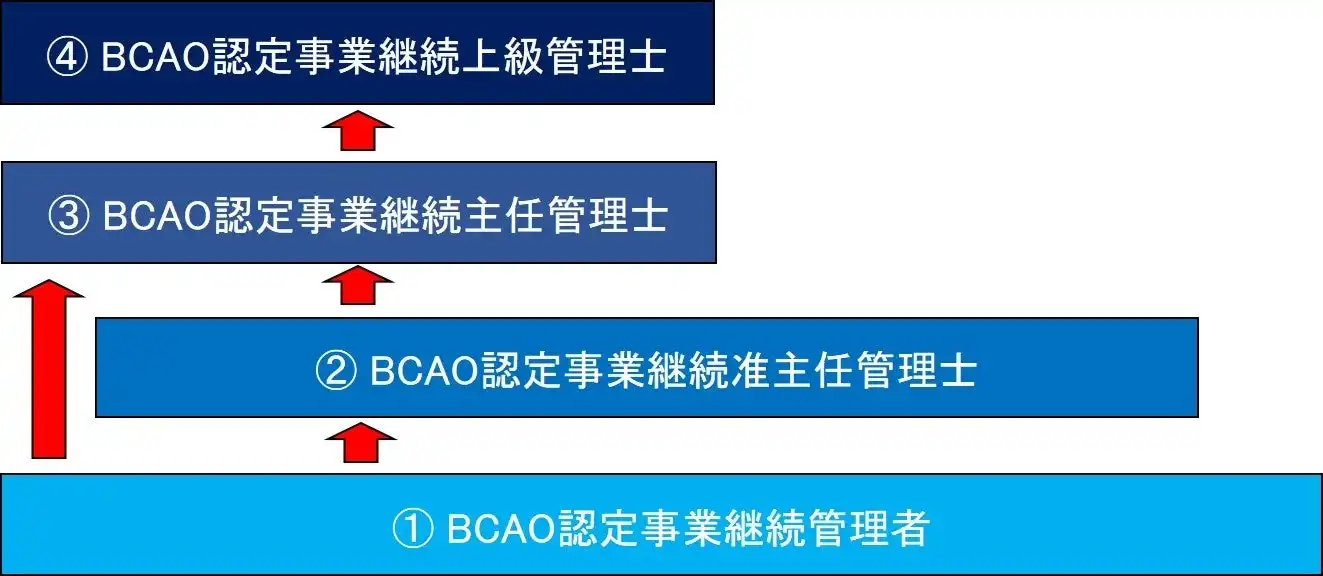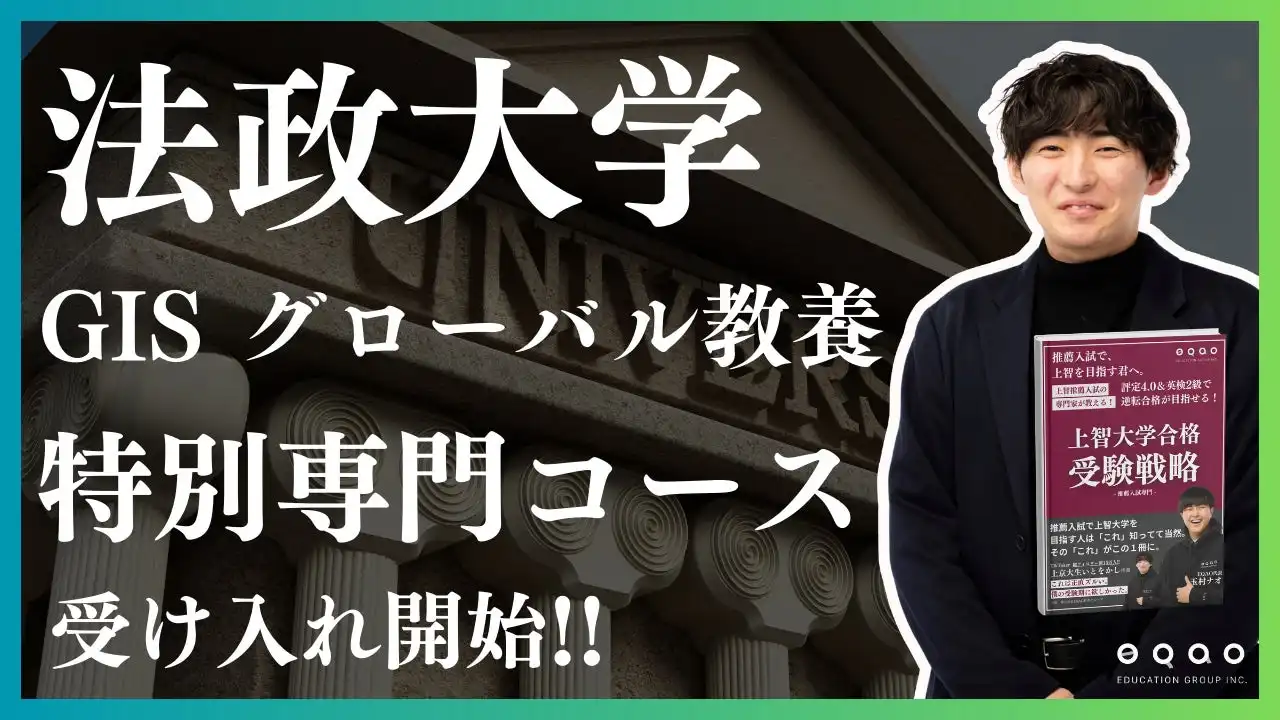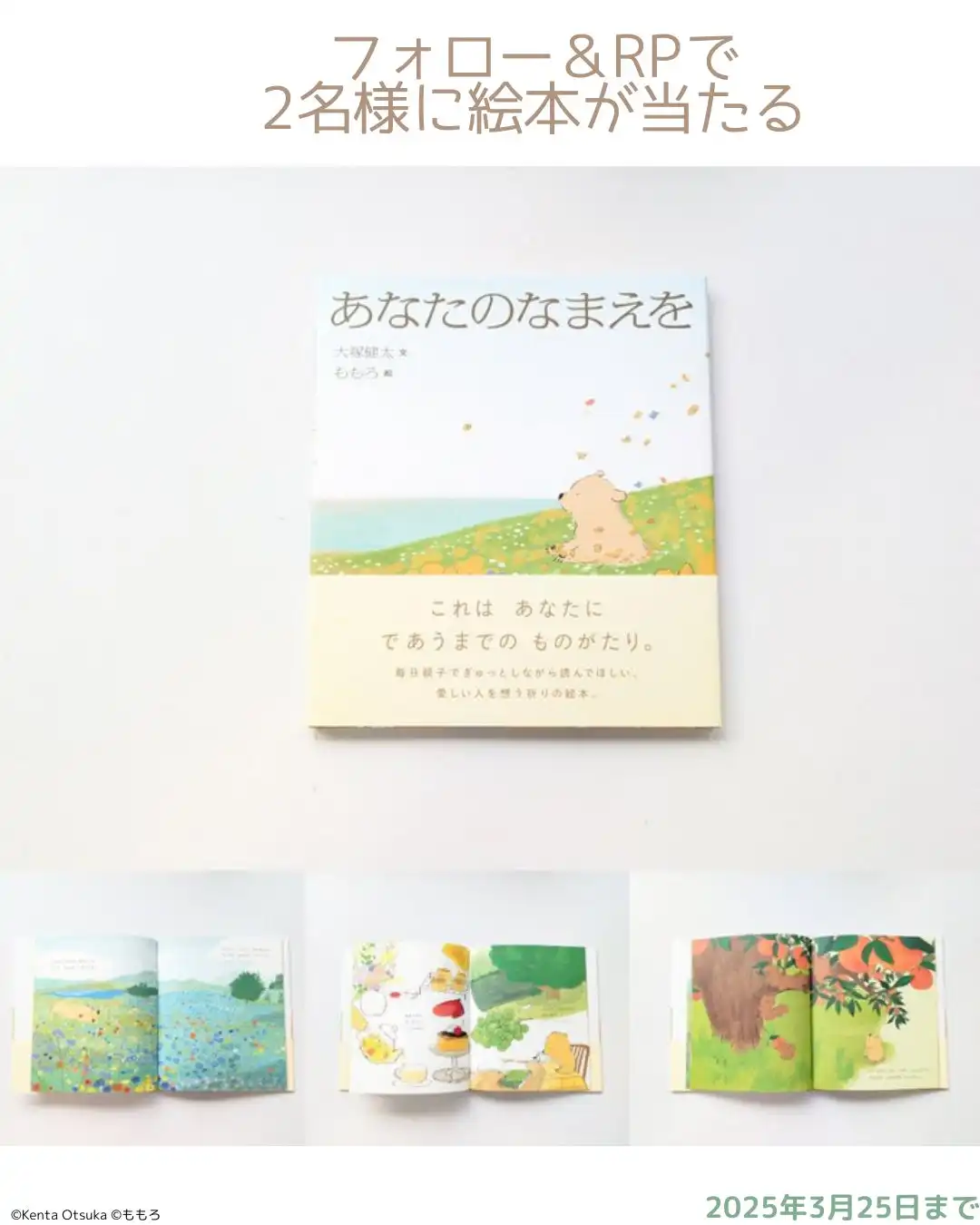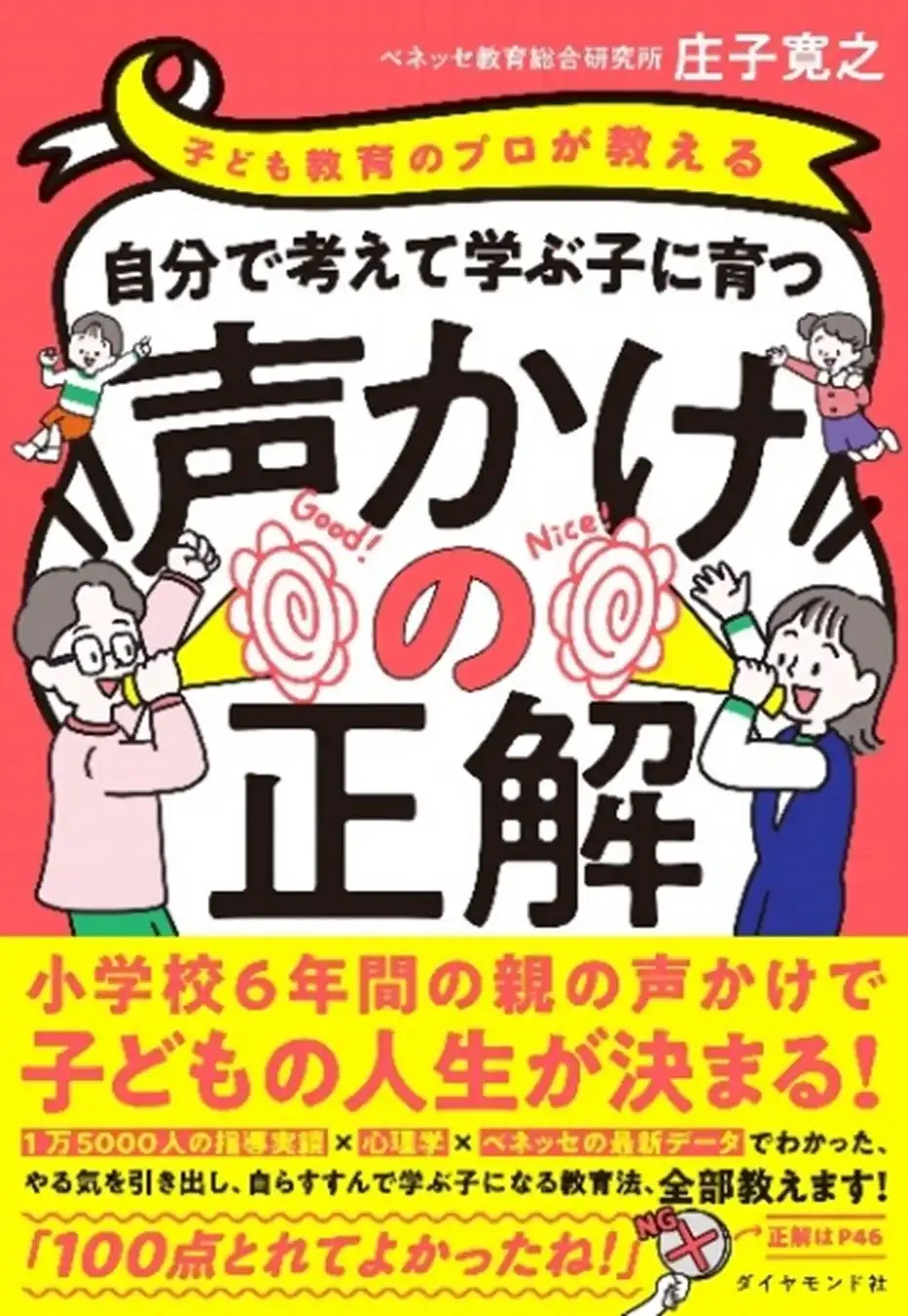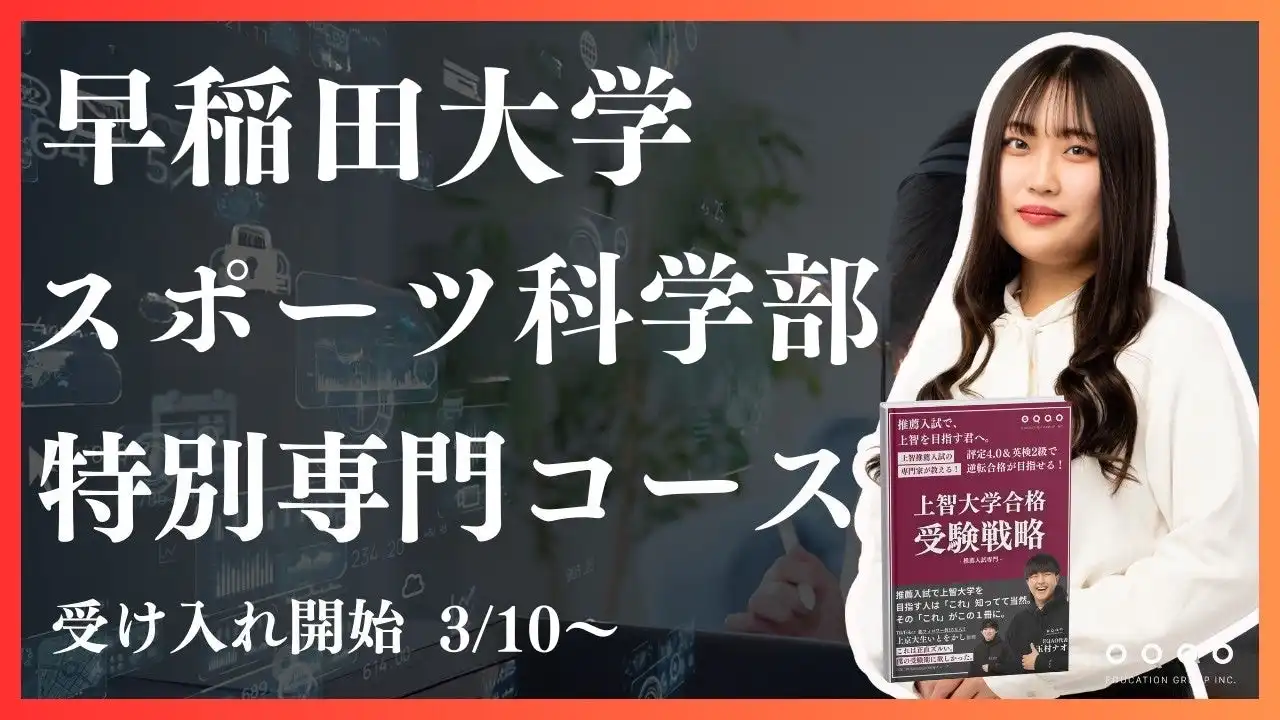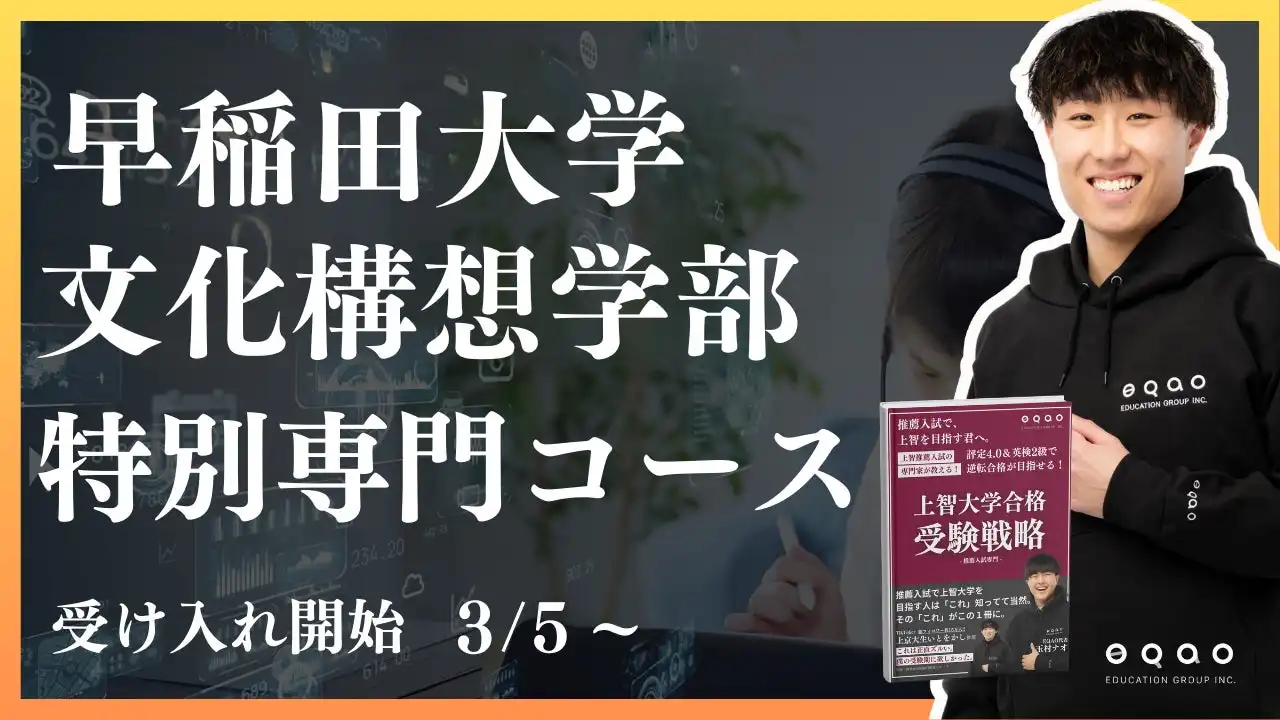全国の保護者の98%が子どものマネー教育の必要性を実感、小学校低学年までの開始を重視する傾向が明らかに

記事の要約
- 子どものマネー教育、保護者の98%が必要性を認識
- マネー教育開始は小学校低学年までが約7割の意見
- 買い物の仕方や働くことを重視した生活密着型の教育が重要
全国の保護者のマネー教育への意識調査結果
アクトインディ株式会社が子どものマネー教育の必要性や取り組みについて、全国のお出かけ施設やレジャー施設に向けた課題解決メディア「いこーよ総研」にて2024年12月2日から実施したユーザーアンケートの結果を公開した。調査結果によると保護者の98%がマネー教育の必要性を感じており、その中でも77%が「とても必要だと思う」と回答している。
マネー教育の開始時期について、小学校1~2年生になったらという回答が41%で最も多く、未就学児からという回答も21%存在し、小学校低学年までには何らかのマネー教育が必要と考える保護者が約68%に上っている。年齢別の実施状況を見ると、0-2歳では8%だが3-5歳で36%、6-8歳で53%、9-12歳では58%と年齢が上がるにつれて実施率が上昇している。
教育内容としては「買い物の仕方」が77%で最も高く、次いで「お金を稼ぐこと、働くことについて」が71%となっている。キャッシュレス化が進む中で、お金の価値や働くことの大切さを子どもに伝えたいという保護者の意識が強く表れており、「お金の貯め方」についても50%の保護者が重要視している。
マネー教育に関する調査結果まとめ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 調査期間 | 2024年12月2日~2025年1月5日 |
| 調査対象 | いこーよ及びいこーよアプリを利用したユーザー |
| サンプル数 | 377サンプル |
| 必要性の認識 | とても必要77%、少しは必要21% |
| 重視する教育内容 | 買い物の仕方77%、働くことについて71%、お金の貯め方50% |
マネーリテラシーについて
マネーリテラシーとは、金銭や金融に関する知識や判断力のことを指し、主な特徴として以下のような点が挙げられる。
- 日常的な金銭管理から資産運用まで幅広い知識が必要
- 社会生活を送る上で不可欠な基礎的能力
- 早期からの段階的な教育が効果的
マネーリテラシーの向上は、キャッシュレス社会の進展に伴いますます重要性を増している。特に子どもの教育においては、98%の保護者が必要性を感じており、買い物の仕方や働くことの大切さを伝えることから始めるケースが多くなっている。
子どものマネー教育に関する考察
マネー教育の必要性は保護者の間で広く認識されているが、具体的な教育方法や開始時期については課題が残されている。特に0-2歳での実施率が8%と低く、3歳以降に急激に上昇する傾向は、幼児期における適切な教育方法の確立が求められている証左だろう。
キャッシュレス決済の普及により、子どもたちが実物の現金に触れる機会が減少している点も大きな課題となっている。金銭の価値や重要性を実感として理解させるためには、日常生活における具体的な体験機会の創出が不可欠だ。保護者自身の金融リテラシー向上と、それを子どもに伝える教育スキルの習得が今後の重要な課題となるだろう。
教育現場と家庭の連携強化も重要な検討事項となっている。学校教育における体系的なカリキュラムの整備と、家庭での実践的な教育活動の両輪がうまく機能することで、より効果的なマネー教育が実現できるはずだ。今後は、年齢に応じた教材開発や指導方法の確立が期待される。
参考サイト/関連サイト
- PR TIMES.「子どものマネー教育、保護者の98%が必要性を実感! いつから何を教えるべき?/いこーよ総研ユーザーアンケート | アクトインディ株式会社のプレスリリース」.https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000508.000026954.html, (参照 2025-01-16).