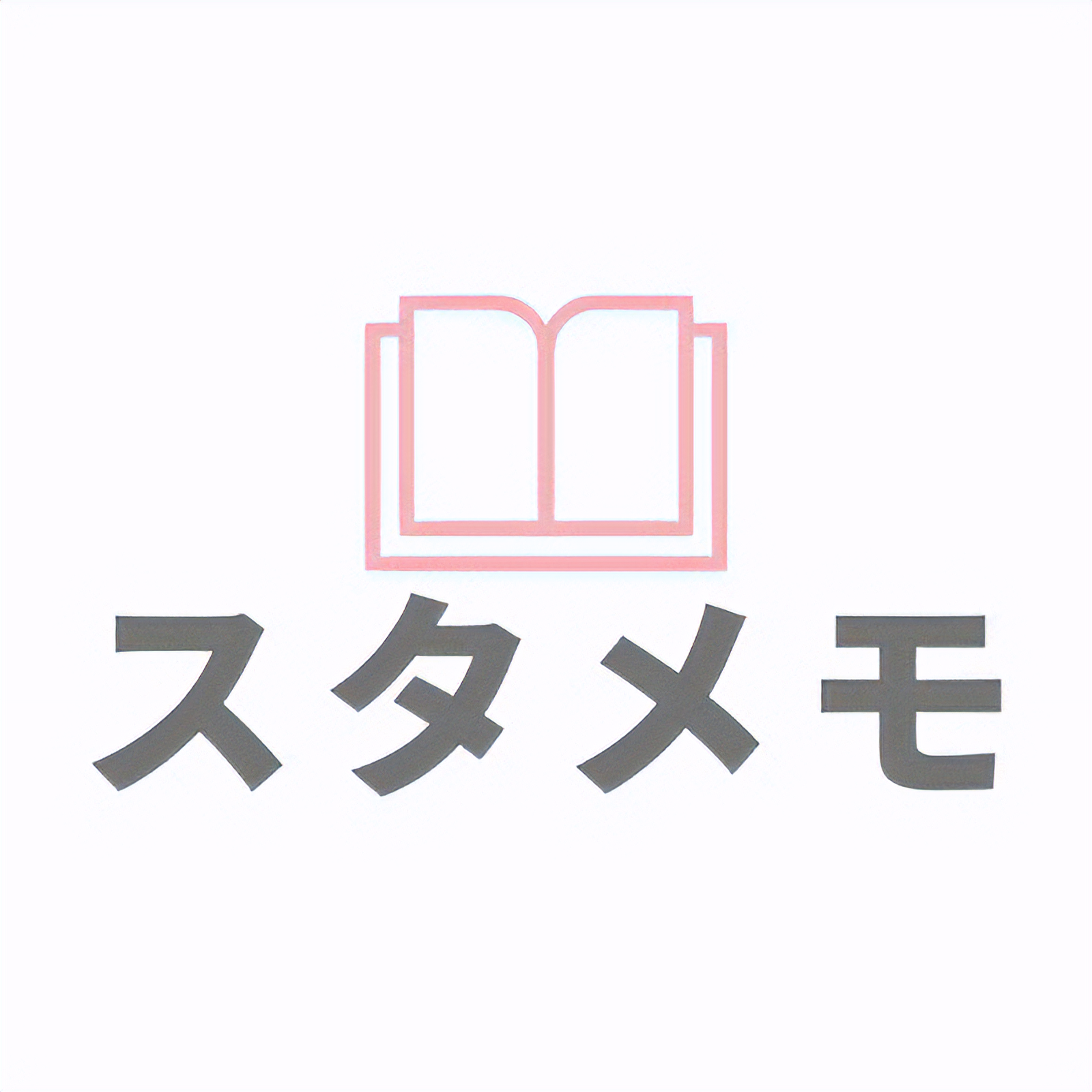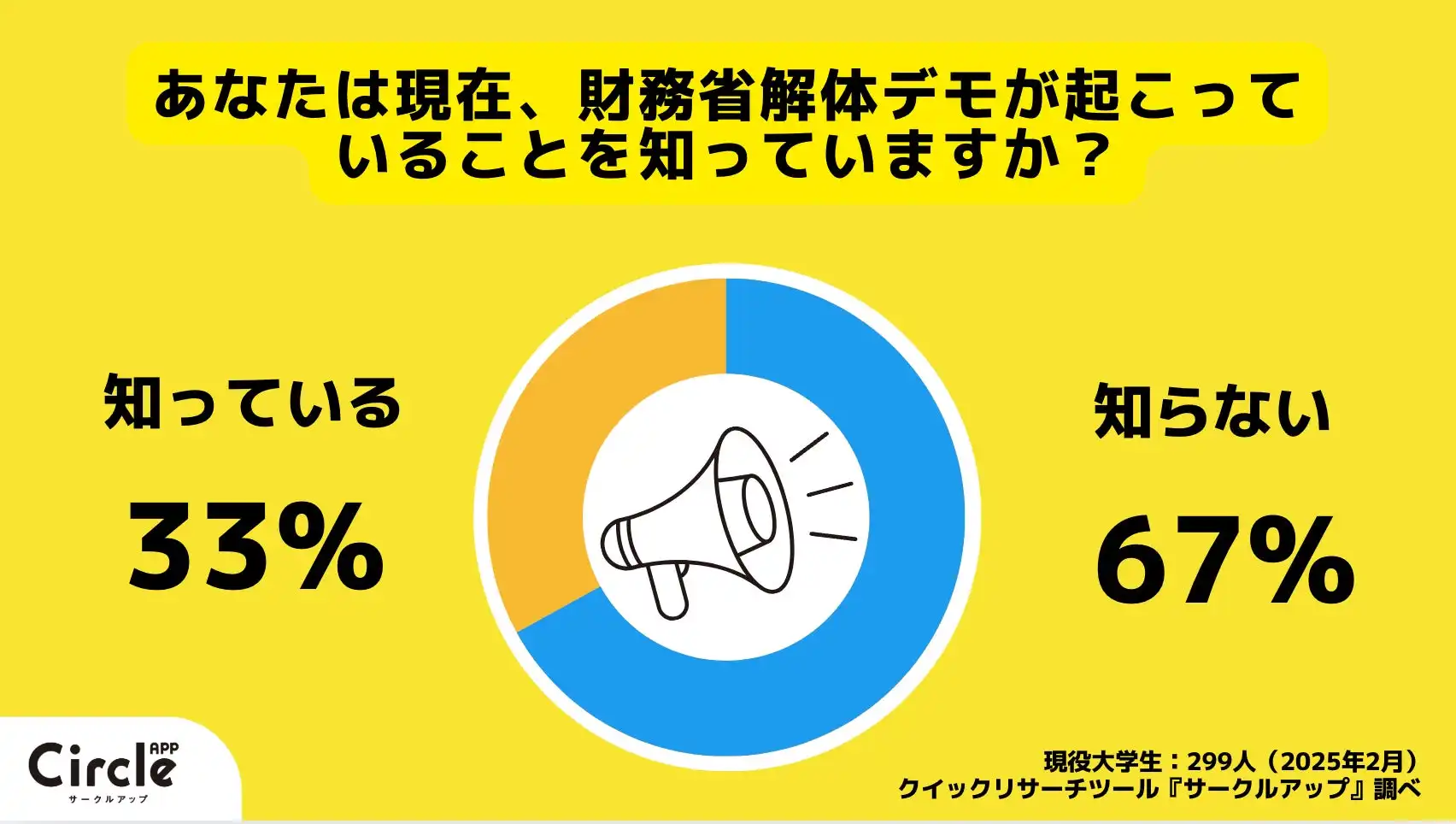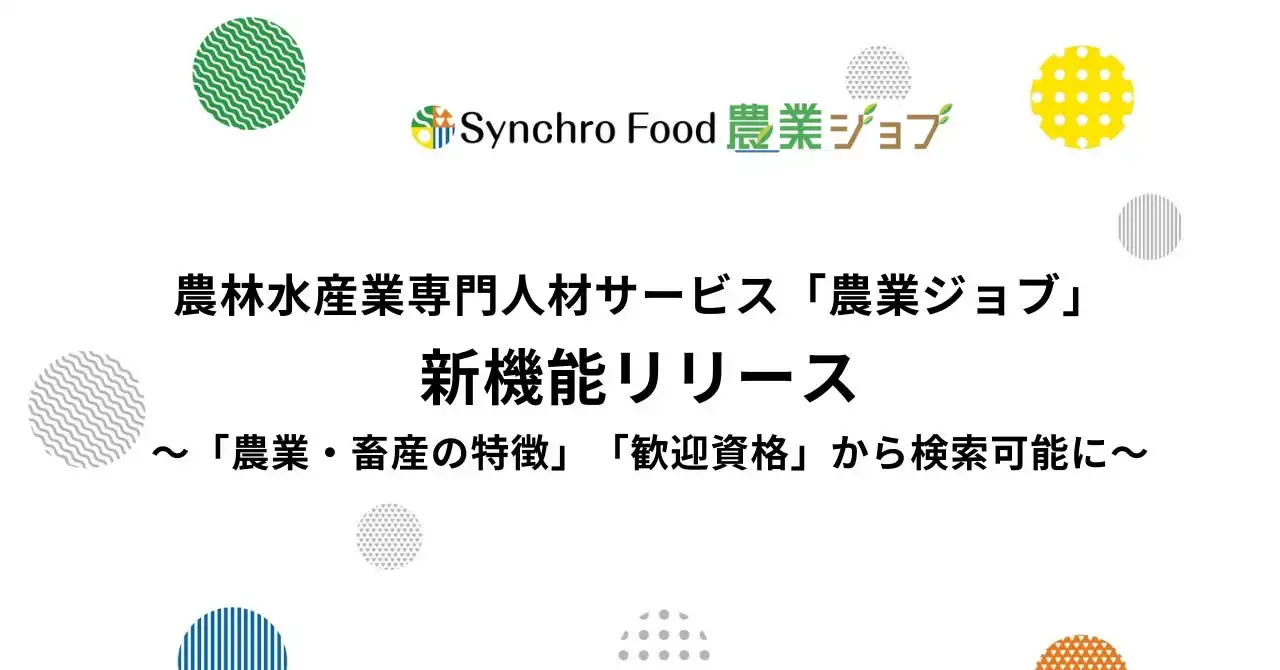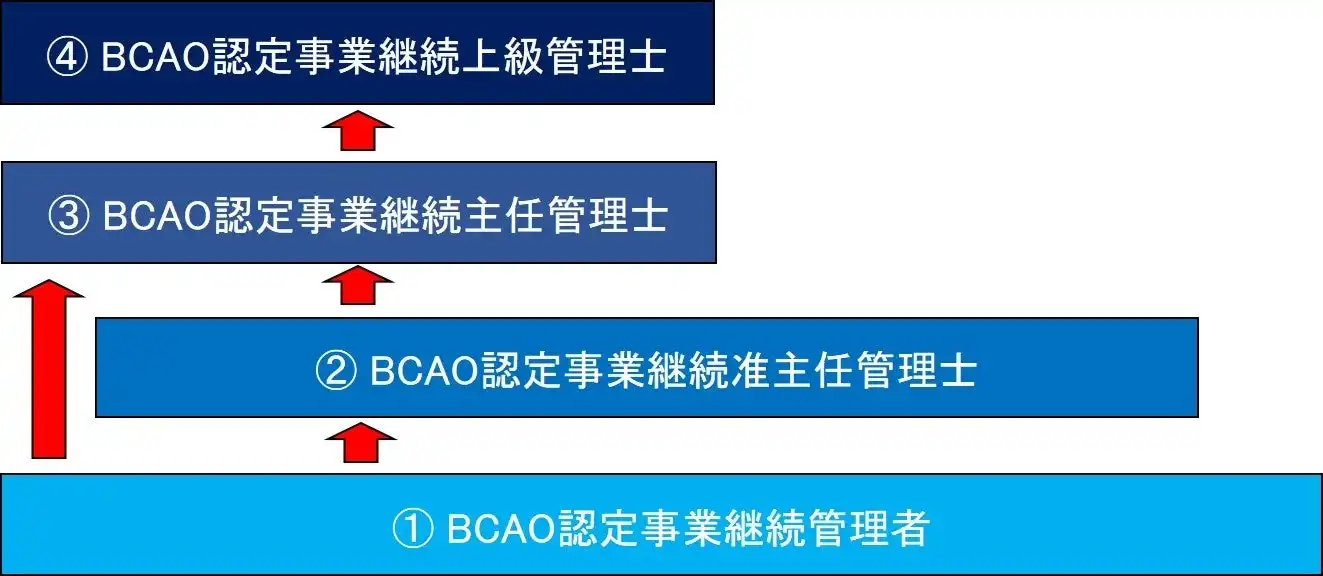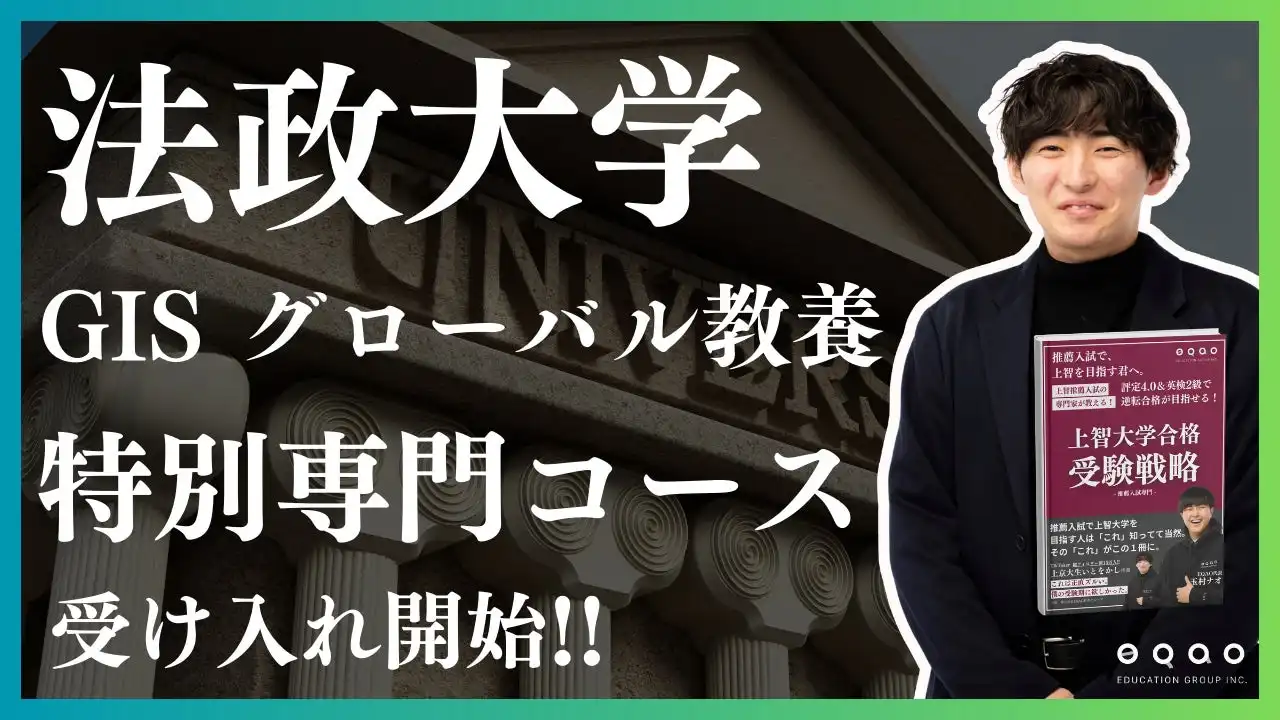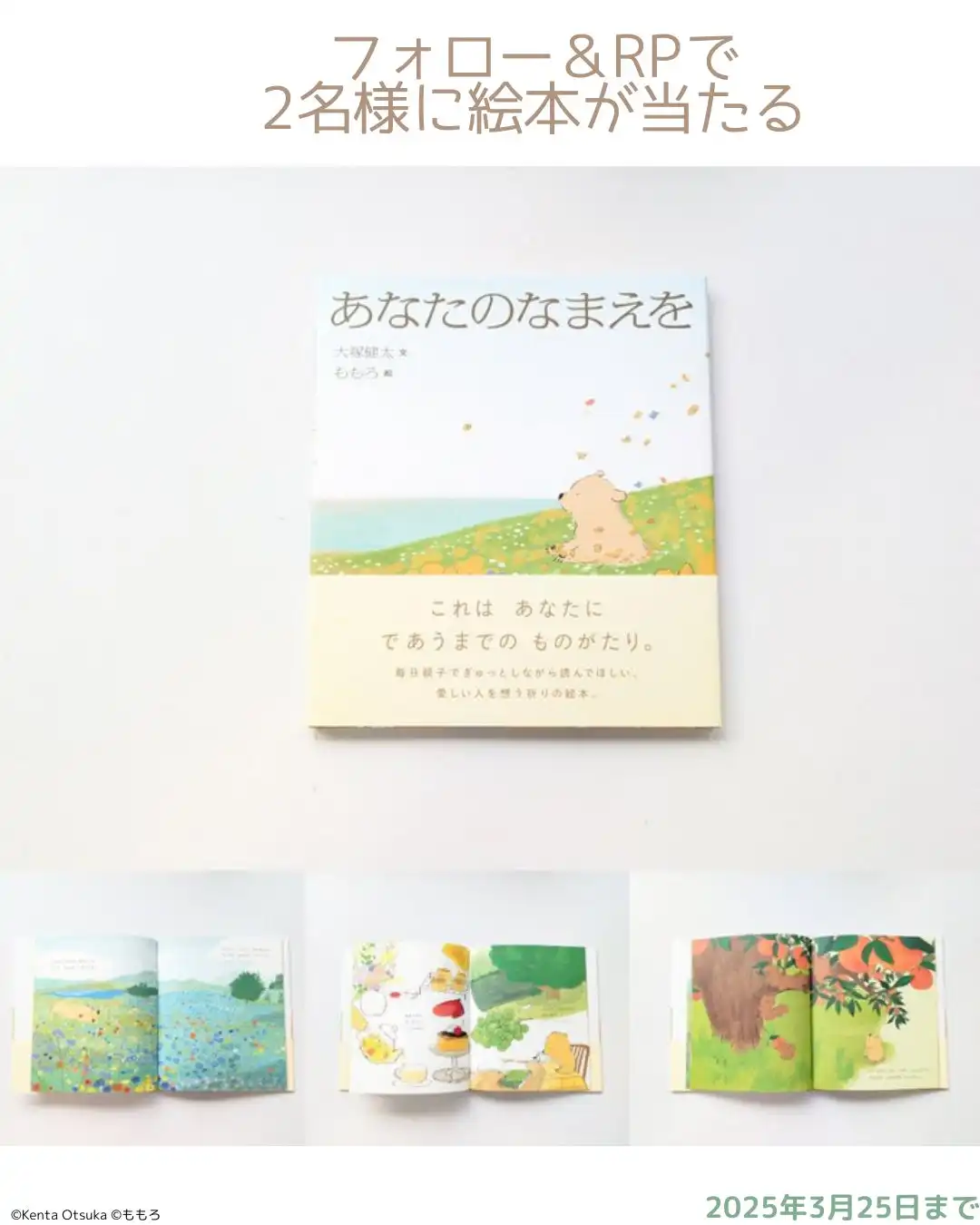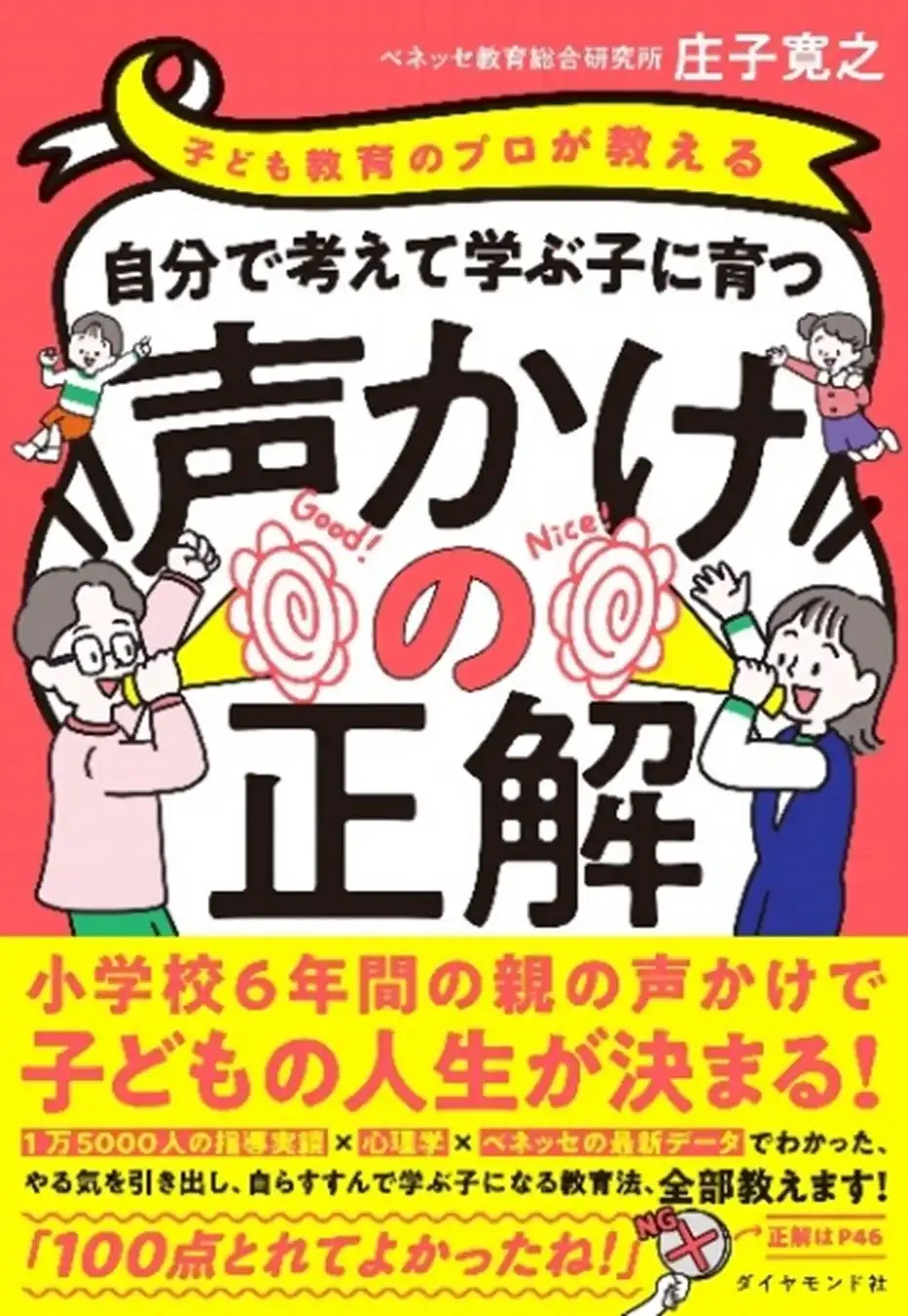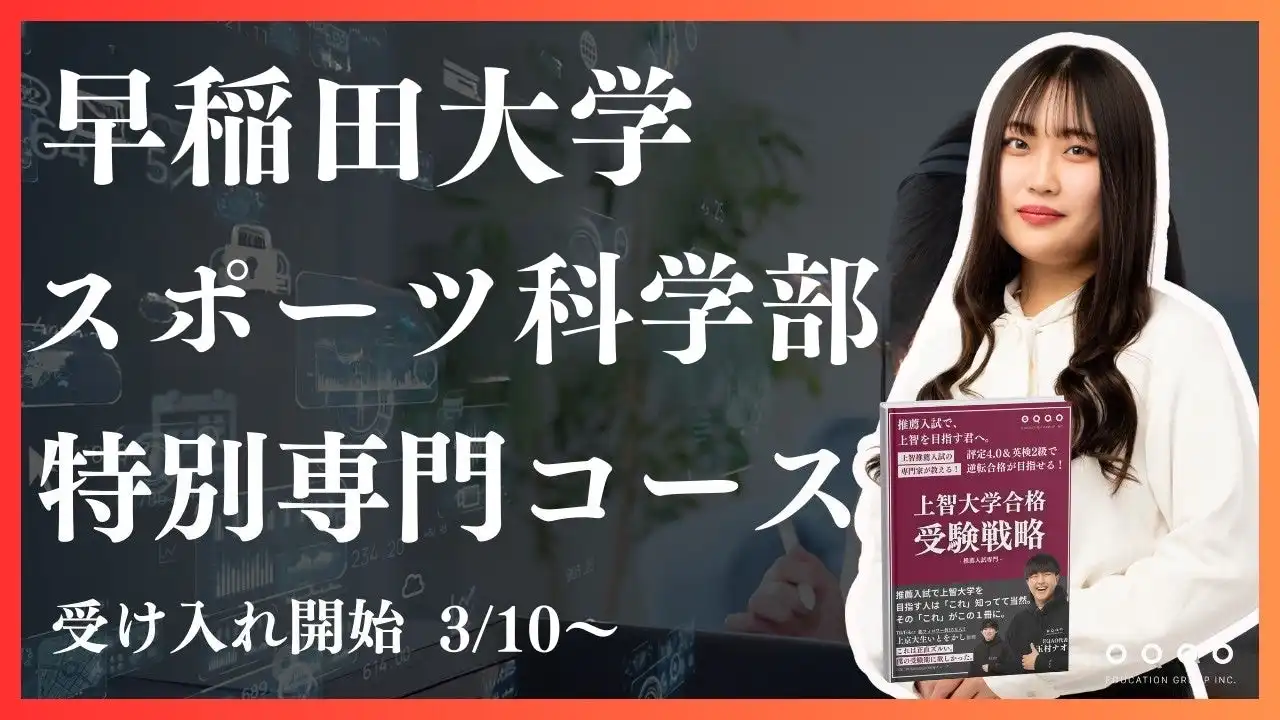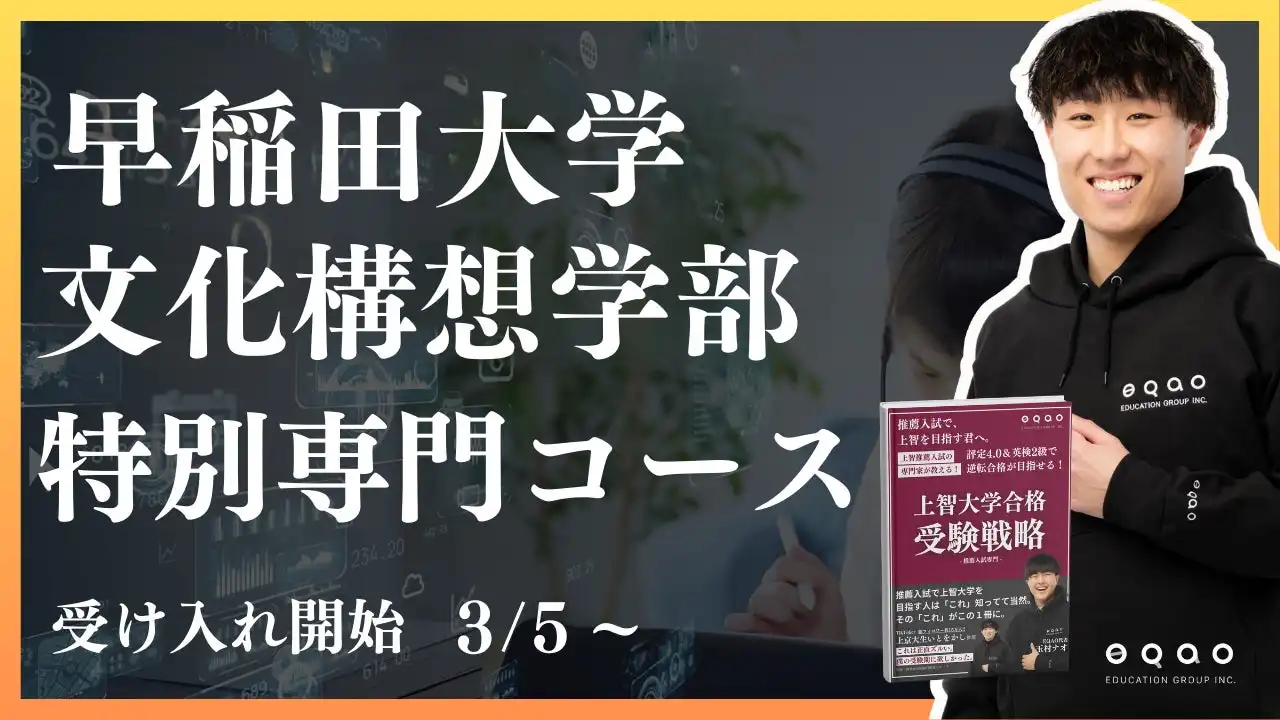早稲田大学田辺新一教授のArchitect’s magazine vol.43特集、建築環境学研究40年の軌跡と快適性追求の成果を紹介

記事の要約
- アーキテクツマガジンvol.43が発刊、田辺新一教授を特集
- 建築環境学の第一人者として快適性とウェルネスを研究
- スマート社会技術融合研究機構の機構長として活動
早稲田大学田辺教授の建築環境学研究が建築業界誌で特集
クリーク・アンド・リバー社のアーキテクト・エージェンシーは、2025年1月20日に建築業界のヒューマンドキュメント誌『Architect’s magazine vol.43』を発刊した。本号では早稲田大学創造理工学部建築学科の田辺新一教授を特集し、約40年間にわたる建築環境学の研究成果と快適性・ウェルネスへの取り組みを紹介している。
田辺教授は現在、早稲田大学スマート社会技術融合研究機構の機構長として、スマート社会の実現に向けた取り組みを推進している。研究者としての豊富な経験と知見を活かし、官民問わず様々なプロジェクトに携わり、建築環境の改善と快適性の向上に貢献し続けている。
また本号では、SANUによる人と自然の共生をテーマとした建築の可能性や、船場BIM CONNECT本部によるBIMを活用したエシカルとデジタルの推進、PERSIMMON HILLS architectsの廣岡周平氏の取り組み、戸田建設の新たな価値創造への挑戦など、建築業界の最新動向も紹介している。
Architect’s magazine vol.43の主な内容
| コーナー | 特集内容 | 担当者/組織 |
|---|---|---|
| 建築家の肖像 | 建築環境学研究と快適性追求 | 田辺新一教授 |
| 事務所探訪 | 人と自然の共生 | SANU |
| 建築DX最前線 | BIMを活用したエシカル推進 | 船場BIM CONNECT本部 |
| 新進気鋭 | 若手建築家の取り組み | 廣岡周平氏 |
建築環境学について
建築環境学とは、建築物内外の環境要素と人間の快適性の関係を研究する学問分野である。以下のような特徴的な研究テーマがある。
- 温熱環境や空気質が人体に与える影響の分析
- 省エネルギーと快適性の両立に関する研究
- スマートビルディングにおける環境制御システムの開発
建築環境学の研究成果は、オフィスビルや住宅などの設計に活かされ、人々の生活の質の向上に貢献している。田辺教授の40年にわたる研究は、理論と実践の両面から建築環境の発展に大きく寄与し、次世代の建築環境のあり方を示唆している。
建築環境学研究の発展に関する考察
建築環境学における快適性とウェルネスの研究は、現代社会における重要性を増している。特にポストコロナ時代においては、室内環境の質と人々の健康への関心が高まっており、建築環境学の知見を活かした新たな建築設計の方向性が求められているだろう。
今後は、AIやIoT技術の発展により、より精緻な環境制御が可能になることが予想される。一方で、これらのテクノロジーの導入にあたっては、プライバシーの保護やデータセキュリティの確保など、新たな課題への対応も必要となるだろう。
建築環境学の研究成果を実践に活かすためには、産学連携のさらなる強化が重要となる。特に、スマート社会の実現に向けては、建築分野だけでなく、情報工学や環境工学など、他分野との学際的な協力が不可欠である。
参考サイト/関連サイト
- PR TIMES.「「快適か、そうでないか」を40年追求し続けた早稲田大学創造理工学部建築学科 教授 田辺新一氏を特集 Architect’s magazine [アーキテクツマガジン] vol.43発刊 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社のプレスリリース」.https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003919.000003670.html, (参照 2025-01-22).