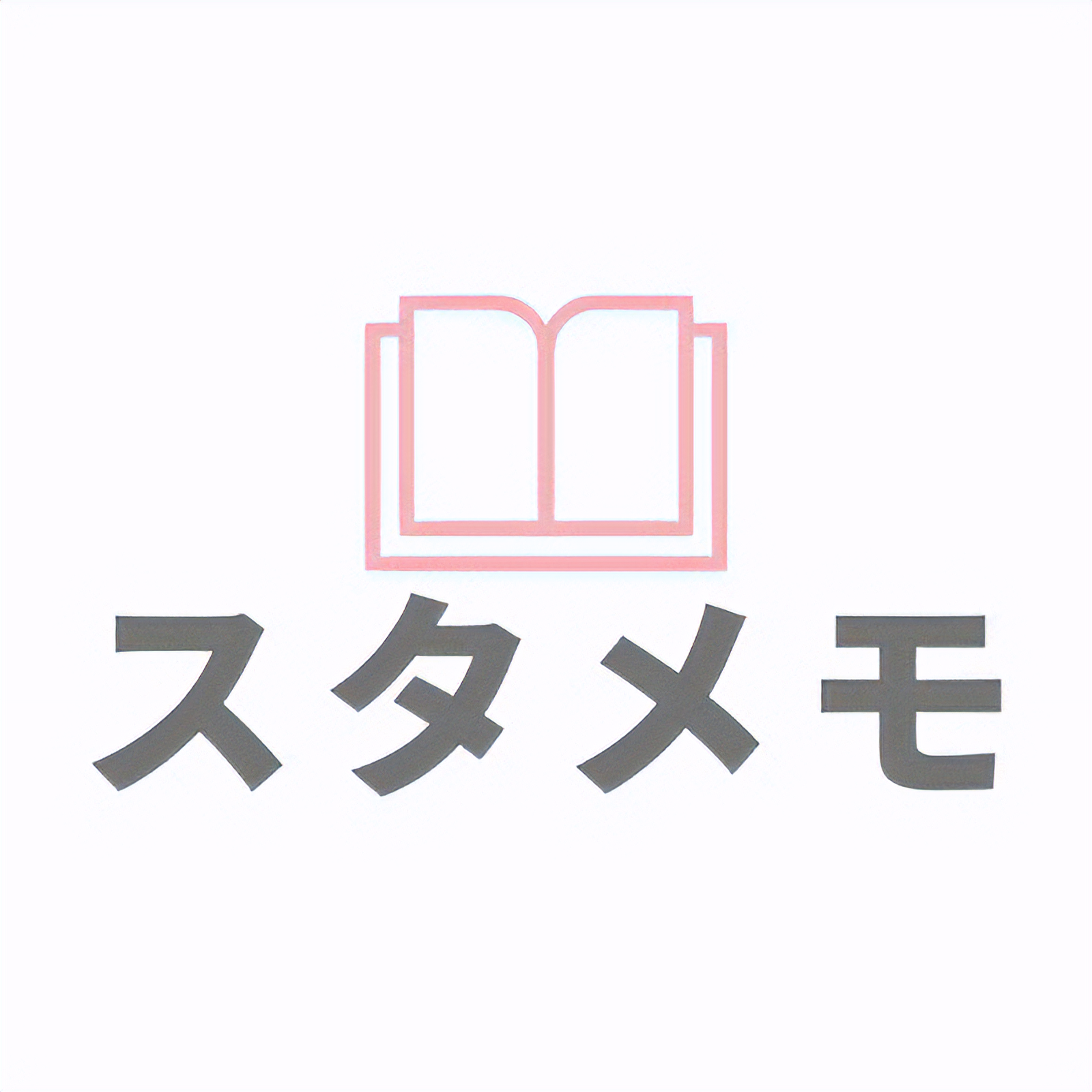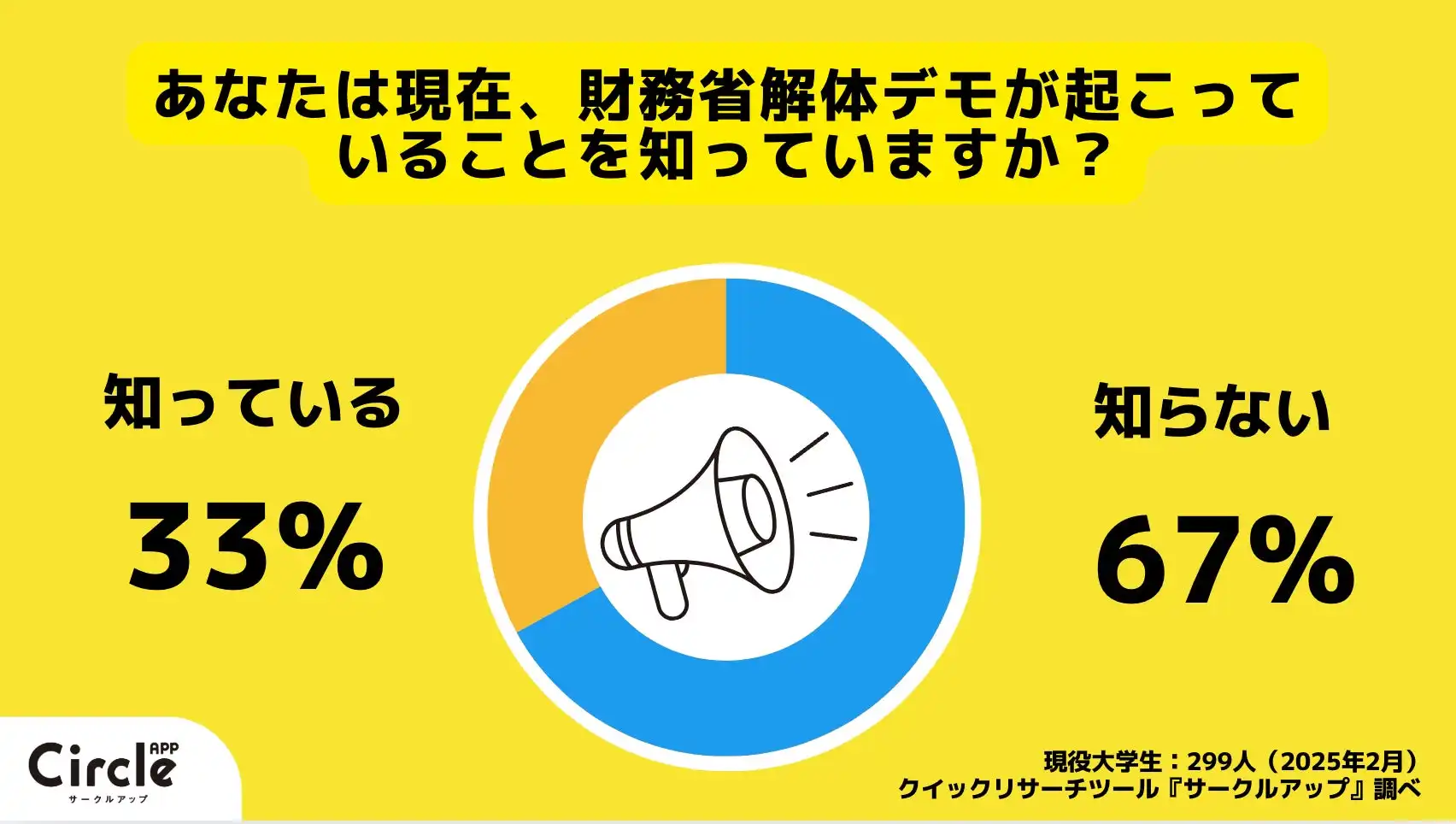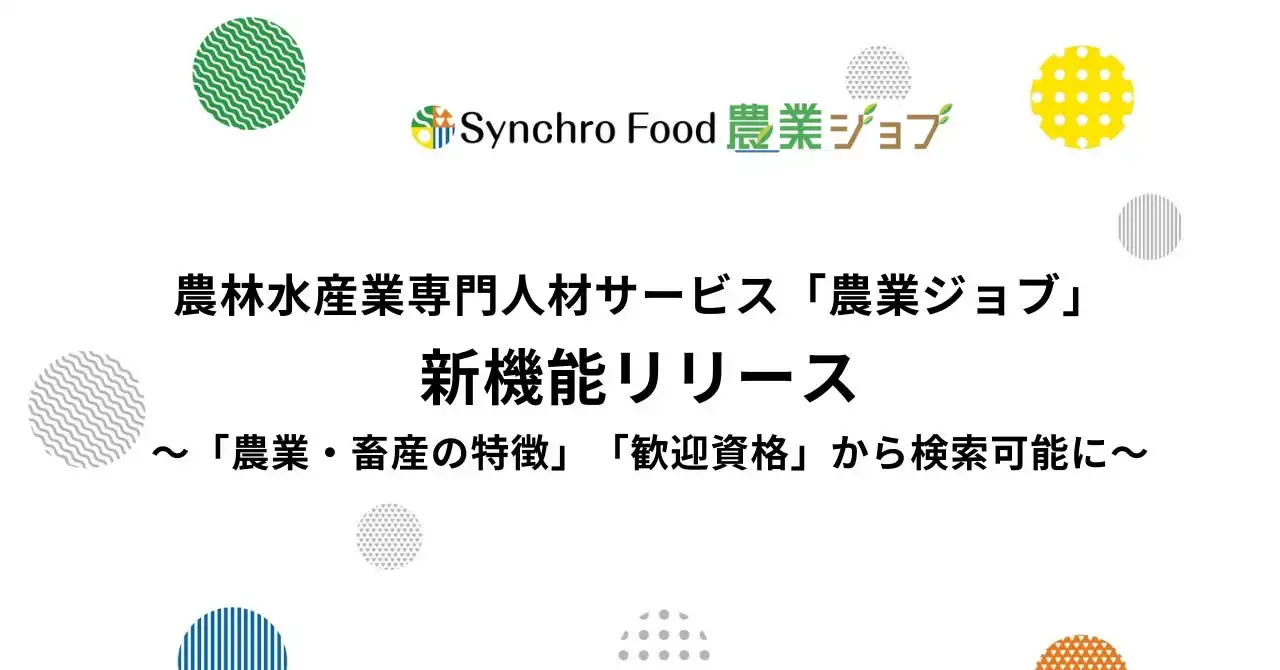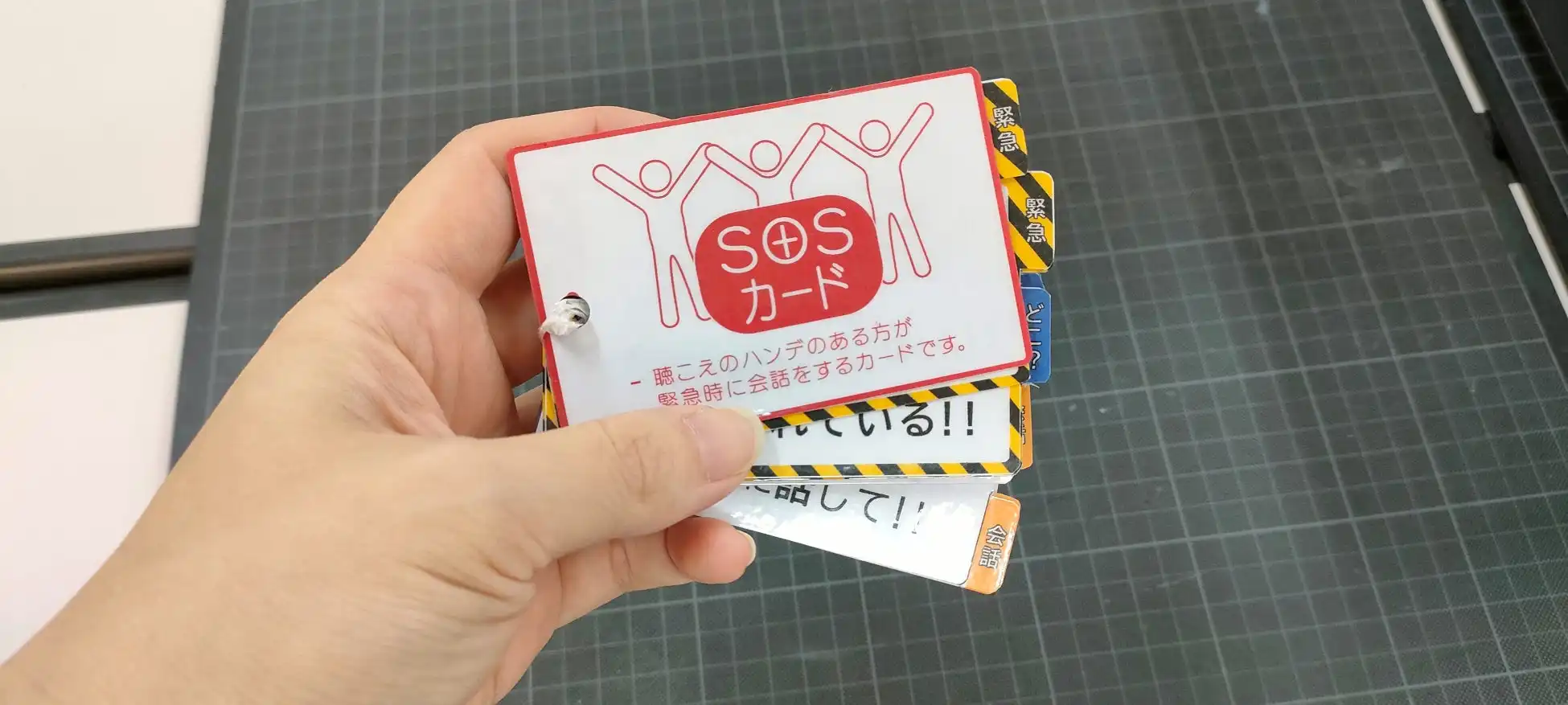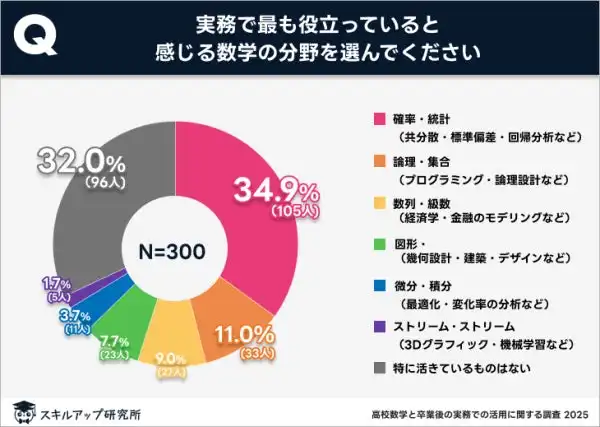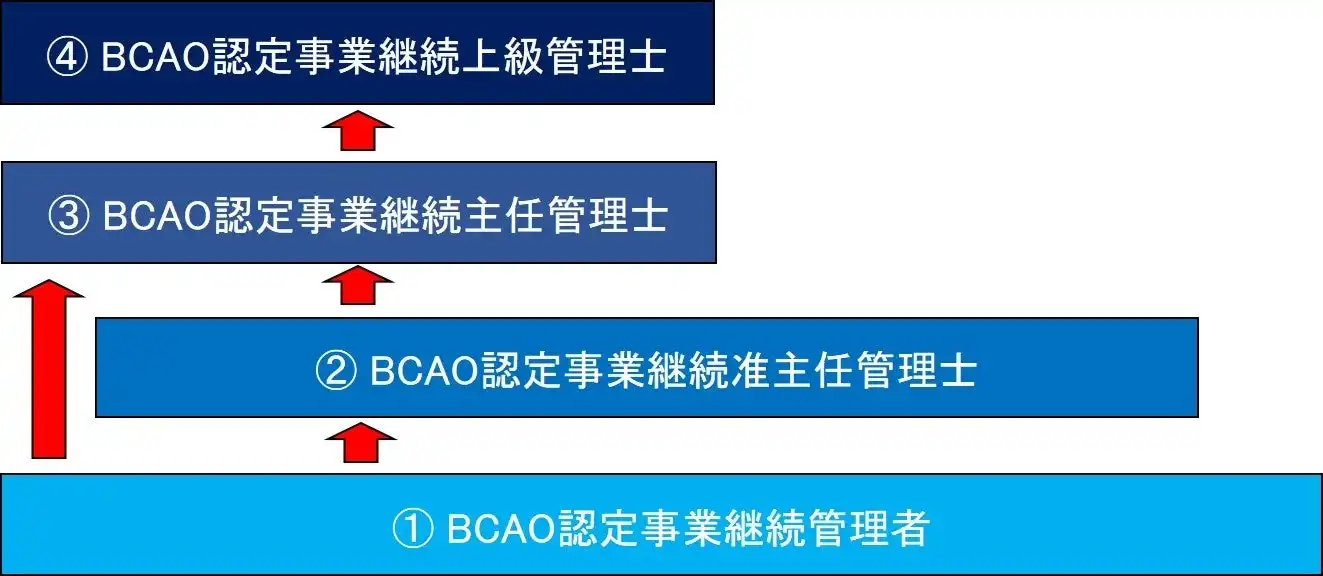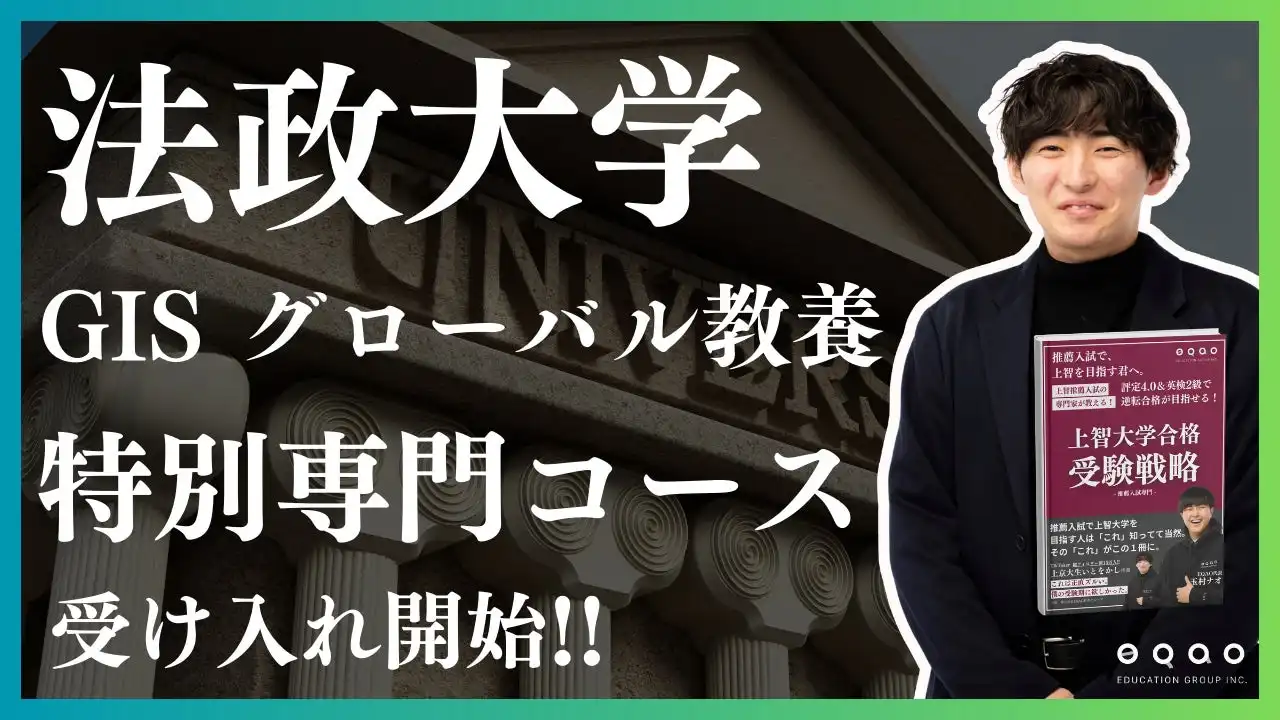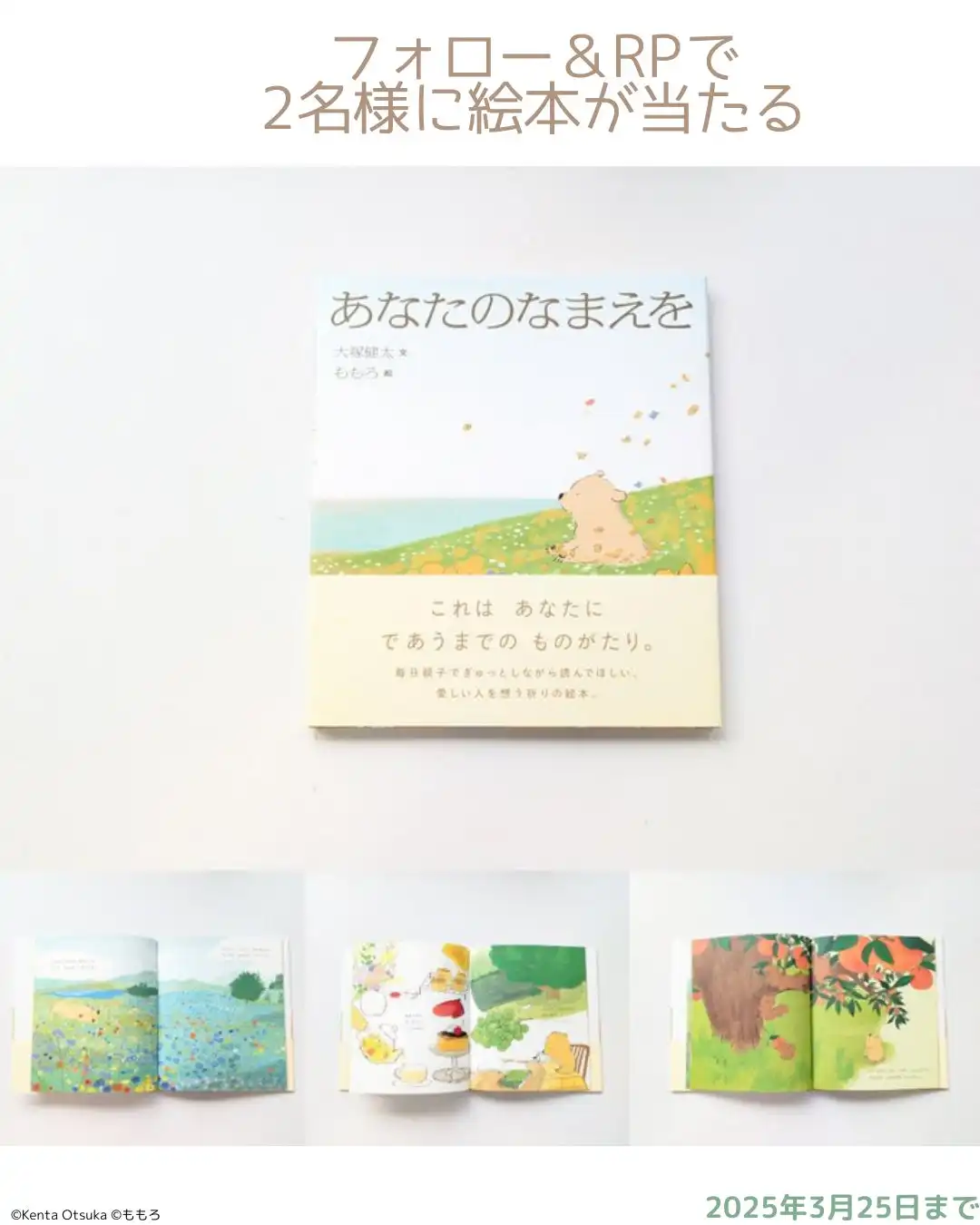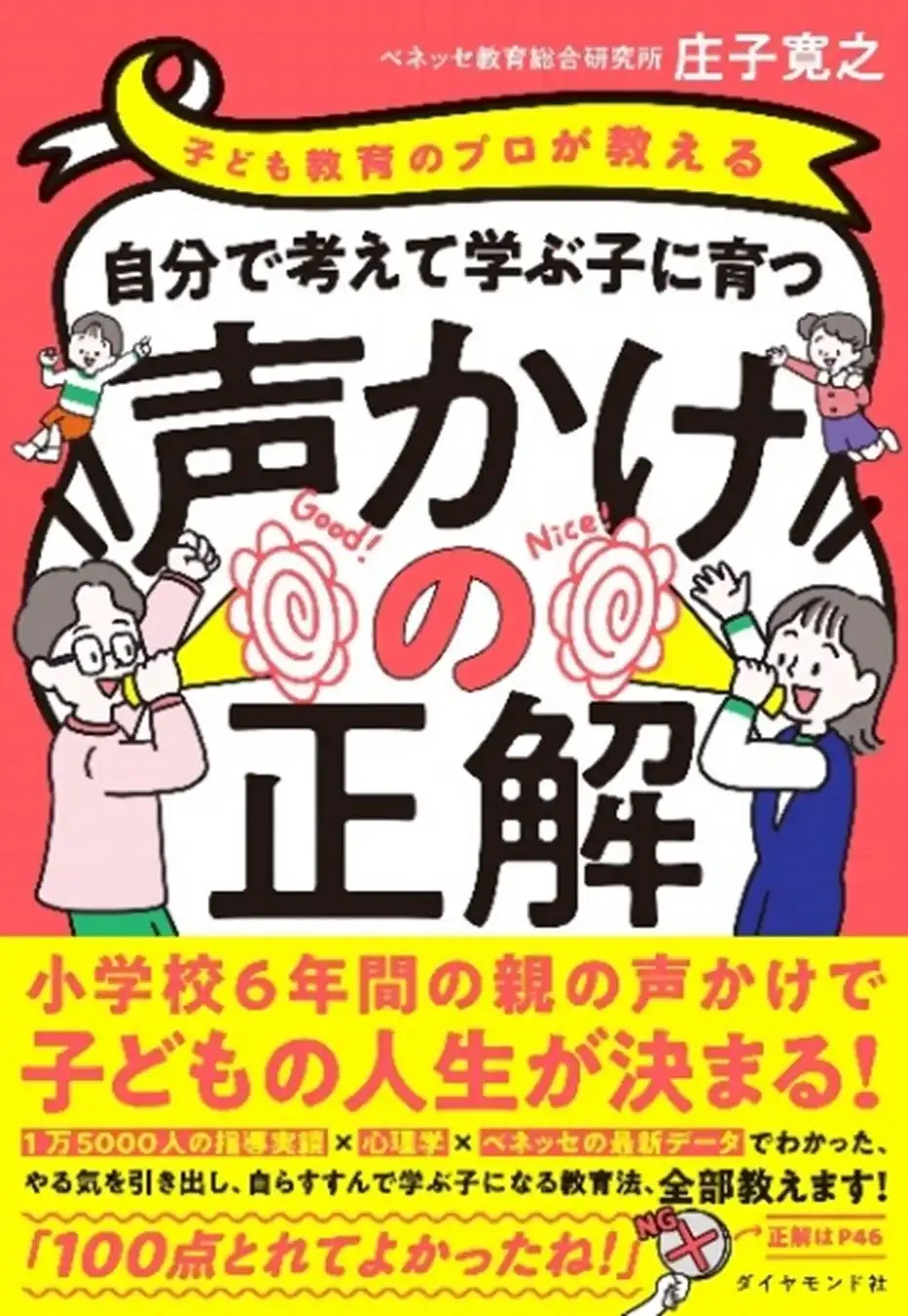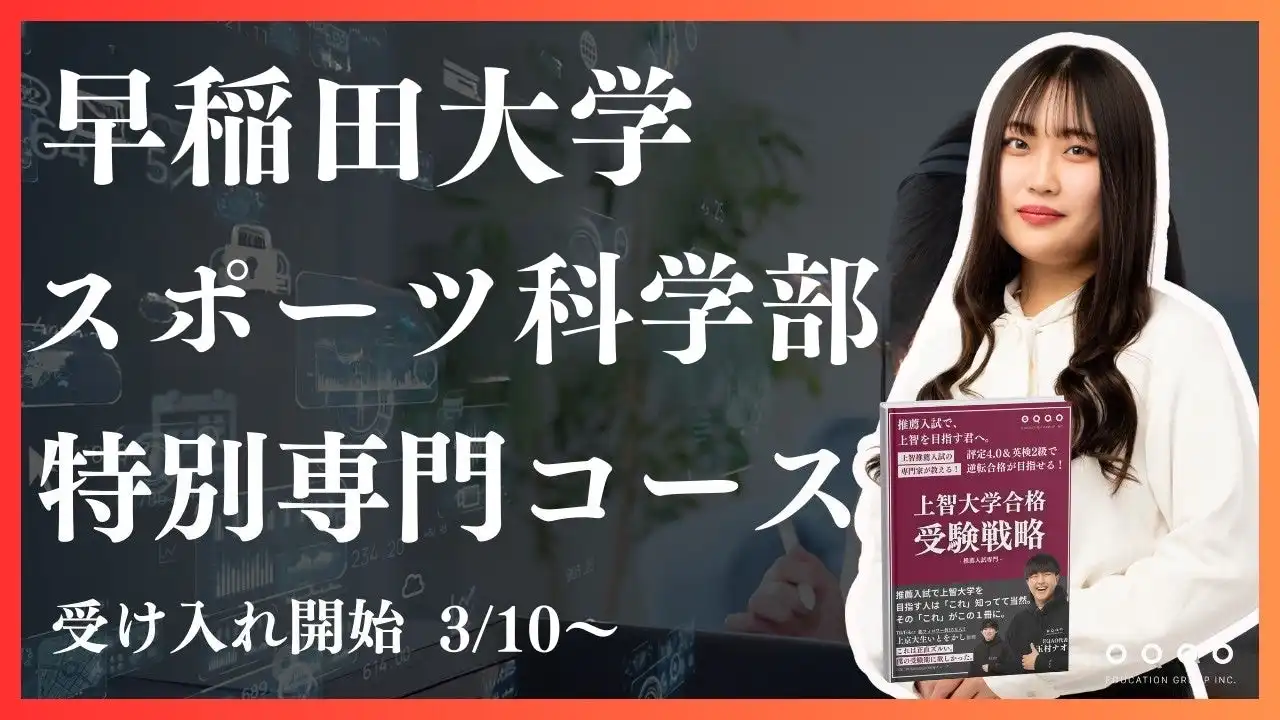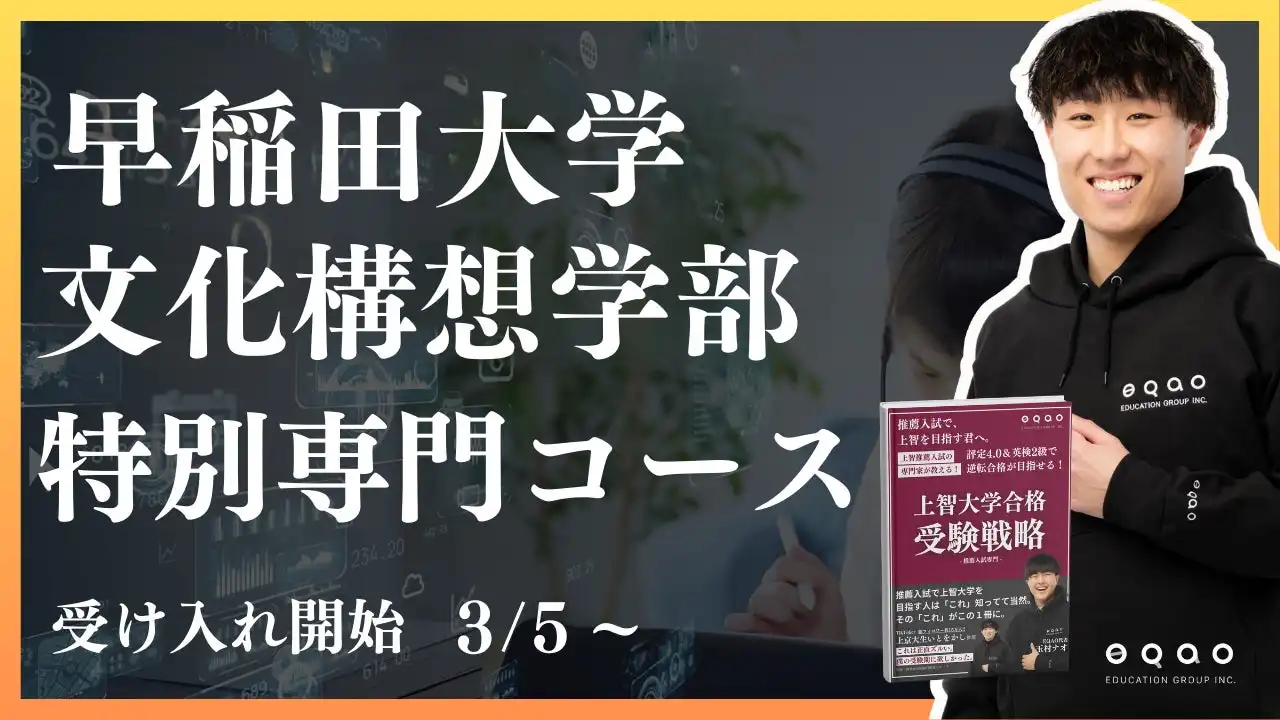ミツカンと日本女子大学が食育プロジェクトを展開、家族の共食時間創出に向けた4つのコンテンツを開発

記事の要約
- ミツカンと日本女子大学が共同で食育プロジェクトを実施
- 学生14名が4つのオリジナルコンテンツを考案
- 家族の共食時間増加を目指した取り組みを展開
ミツカンと日本女子大学による共創プロジェクトの展開
ミツカングループは日本女子大学と共同で実施している「にっぽん食プロジェクト」において、2024年10月26日に第二弾となるワークショップを開催した。このワークショップでは日本女子大学食物学科飯田研究室の学生14名が参加し、家族で共有する食事時間の価値向上を目指した取り組みを展開している。
近年の共働き世帯の増加や少子化、ライフスタイルの多様化により、家族での食事時間の確保が困難になっている現状を踏まえ、幼少期における食事体験の重要性に焦点を当てている。農林水産省が掲げる共食機会の増加という目標に沿った取り組みとして、学生たちが独自の視点で4つのオリジナルコンテンツを考案した。
学生たちが考案したコンテンツには、料理ゲームアプリやサブスクリプション型の食材提供サービス、料理レシピ雑誌、カードゲームなど、現代のライフスタイルに合わせた斬新なアイデアが盛り込まれている。これらのコンテンツは家族全員で楽しめる工夫が施されており、食事を通じたコミュニケーションの活性化を促進することが期待される。
オリジナルコンテンツの詳細
| クッキングアドベンチャー | おうち農園定期便 | Family Kitchen | おうち○○トランプ | |
|---|---|---|---|---|
| 主な特徴 | 料理ゲームアプリ | 食材苗の定期配送 | 付録付きレシピ雑誌 | 献立決めカードゲーム |
| 対象者 | 親子 | 家族全員 | 家族全員 | 家族・友人 |
| 期待効果 | 料理体験の記録 | 食育と行事食体験 | 調理スキル向上 | 献立選択の活性化 |
共食について
共食とは、農林水産省が定義する「みんなで一緒に食卓を囲んで共に食べること」を指す概念であり、現代社会における重要な課題として注目されている。以下のような特徴が挙げられる。
- 家族間のコミュニケーション促進効果
- 食育における重要な要素としての位置付け
- 子どもの心身の健全な発達への貢献
にっぽん食プロジェクトの調査によると、幼少期における食事の手伝い頻度が高い人ほど、共食時のコミュニケーションを楽しむ傾向が強いことが判明している。このことから、幼少期の食体験が後の食生活に大きな影響を与えることが示唆されており、共食の重要性が改めて認識されている。
家族の共食時間創出に関する考察
現代のライフスタイルの多様化に対応した新しい形の共食体験を提供することは、家族のコミュニケーション促進において重要な意味を持つ。特にデジタル技術を活用したアプローチは、若い世代の興味を引き付けながら、伝統的な食文化の継承を可能にする効果的な手段となり得るだろう。
今後は、共働き世帯や時間的制約の多い家庭でも実践可能な共食のあり方を模索していく必要がある。オンラインツールやデジタルコンテンツを活用しながら、柔軟な食事時間の設定や、家族で協力して料理を作る機会を増やすための工夫が求められるだろう。
にっぽん食プロジェクトの取り組みは、食育における新たな可能性を示している。今後は、より多くの教育機関や企業との連携を通じて、共食の価値をさらに広めていくことが期待される。デジタルとリアルを組み合わせた新しい食育のあり方が、現代社会における家族の絆を深める一助となるだろう。
参考サイト/関連サイト
- PR TIMES.「ミツカン×日本女子大学「にっぽん食プロジェクト」ワークショップを開催 家族みんなの“ごはん時間(※1)”を増やすための 4つのオリジナルコンテンツを学生が考案 | 株式会社Mizkan Holdingsのプレスリリース」.https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000498.000065533.html, (参照 2025-01-11).