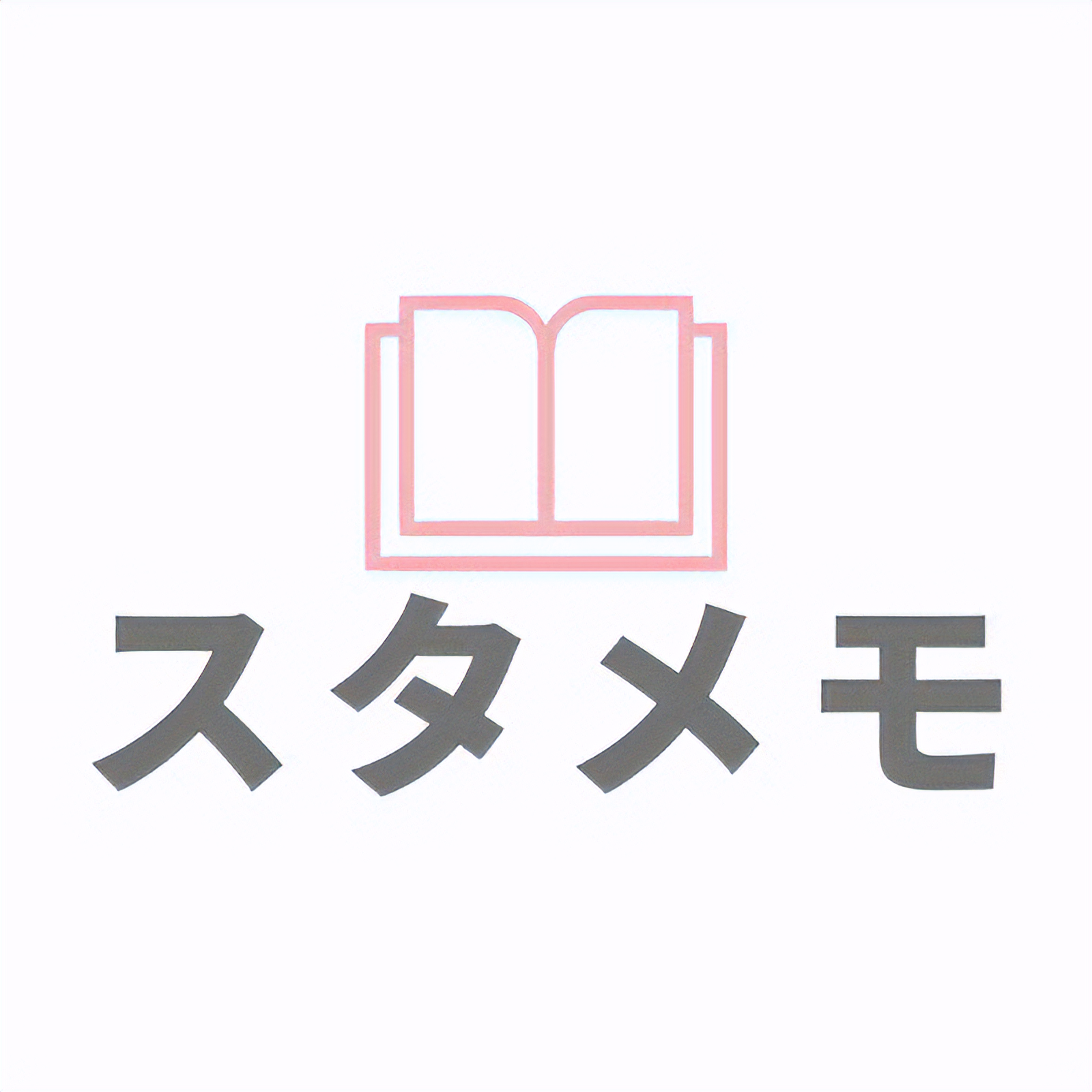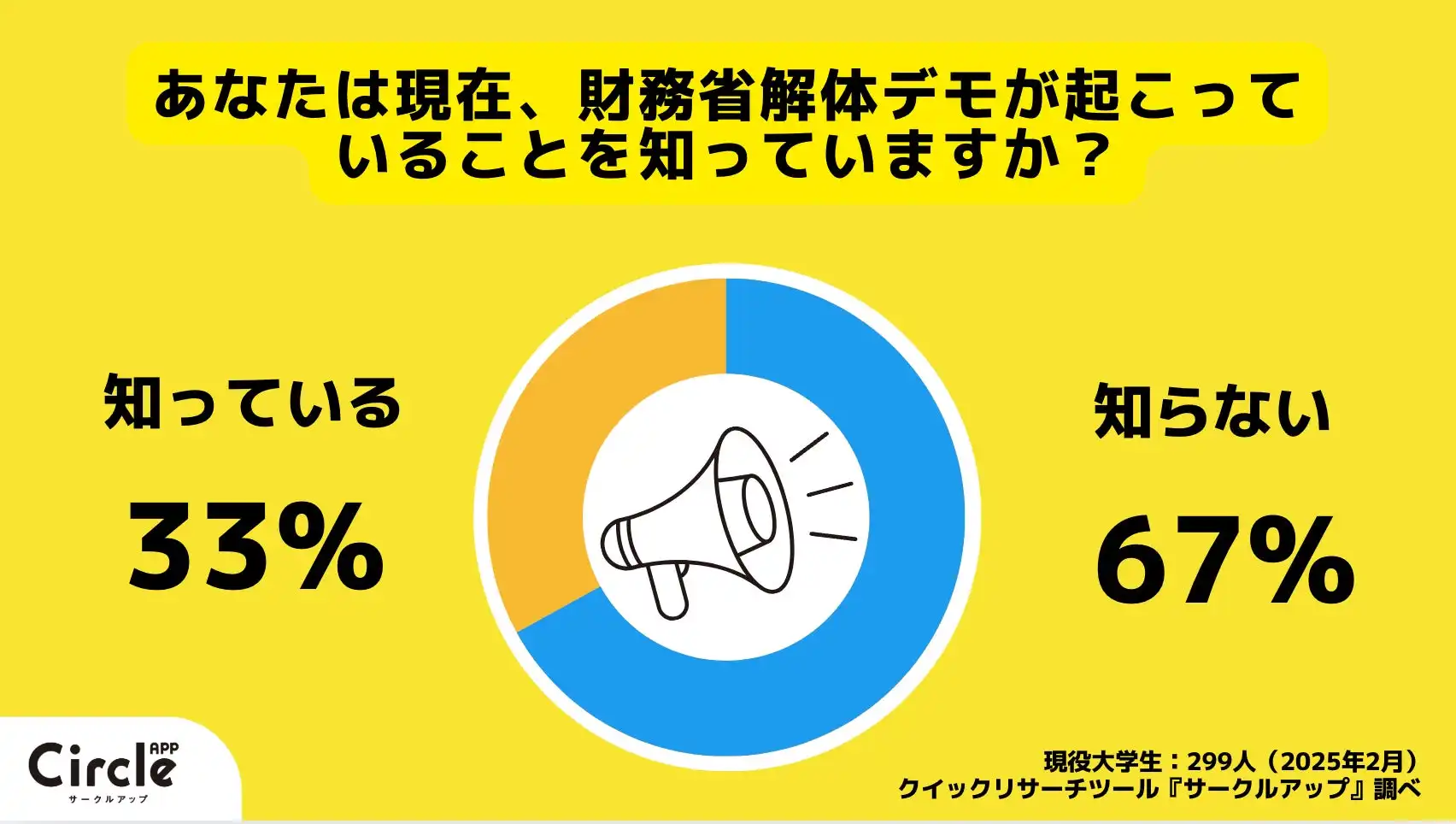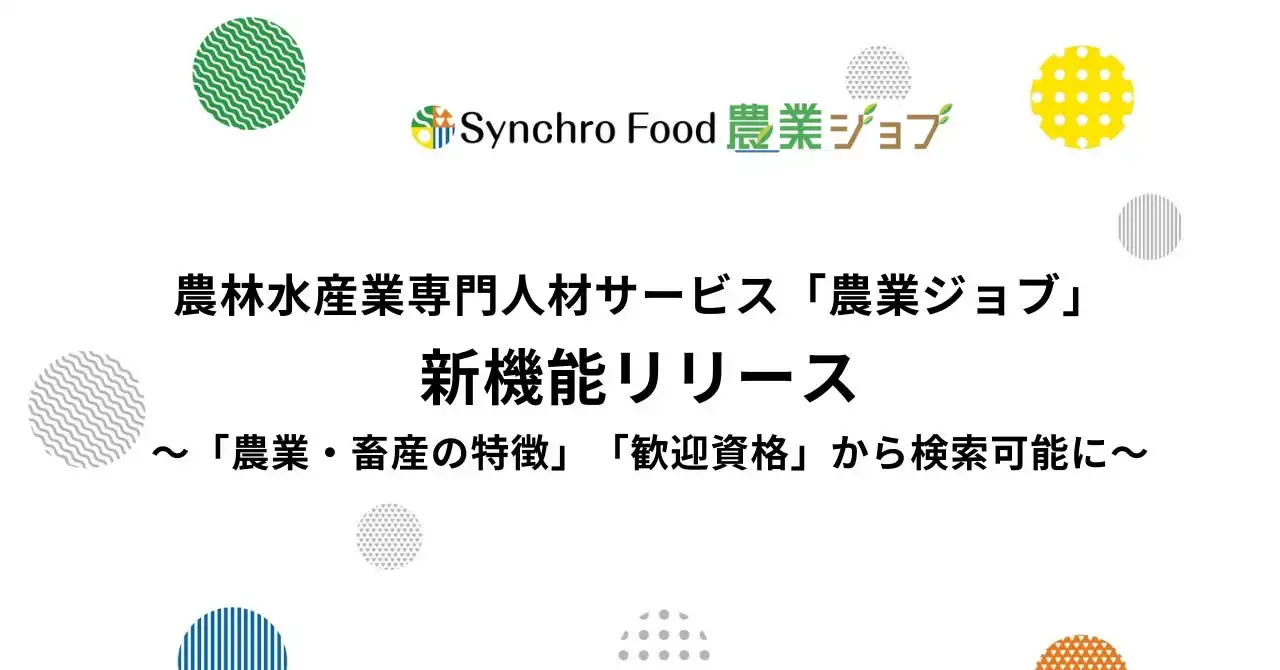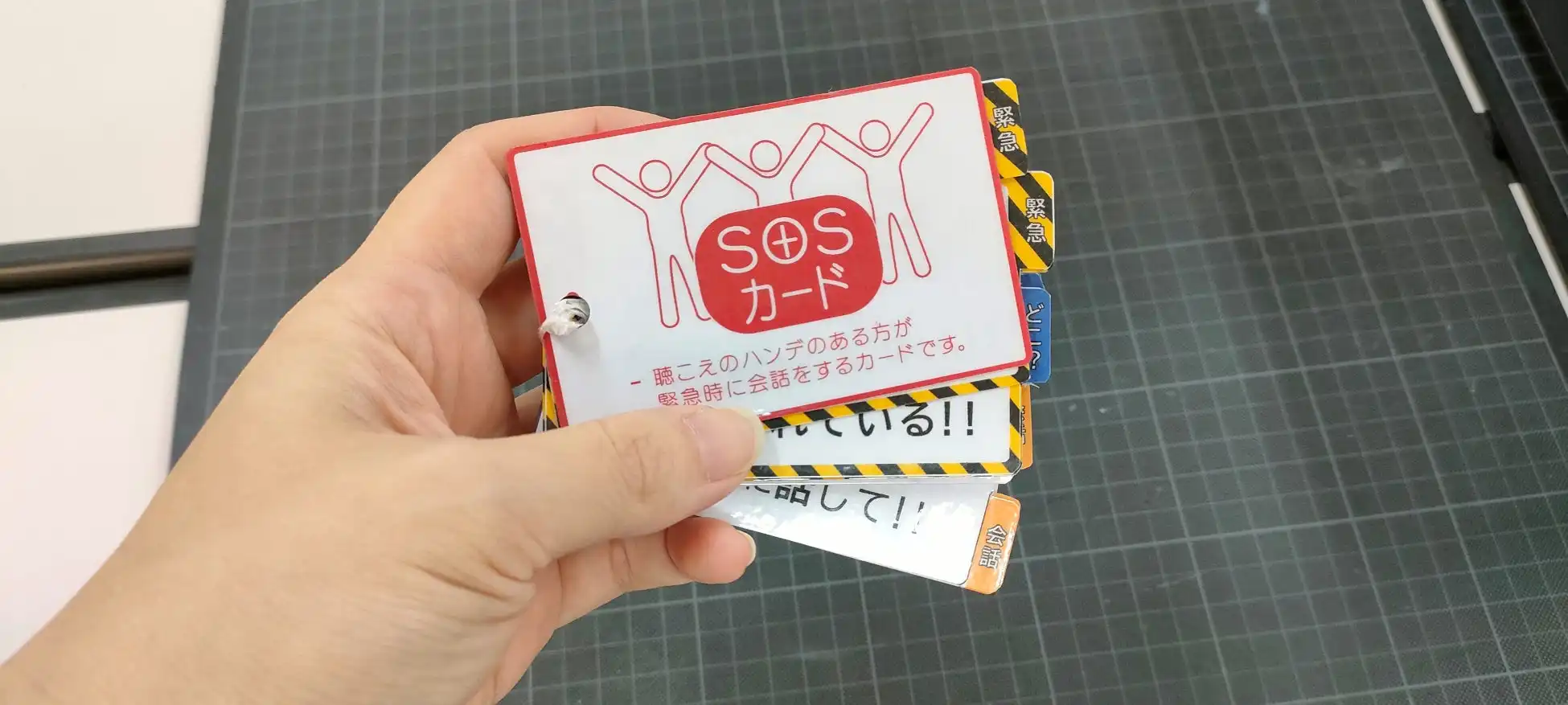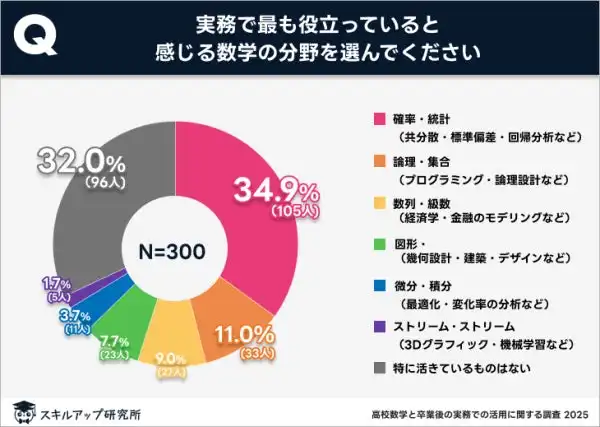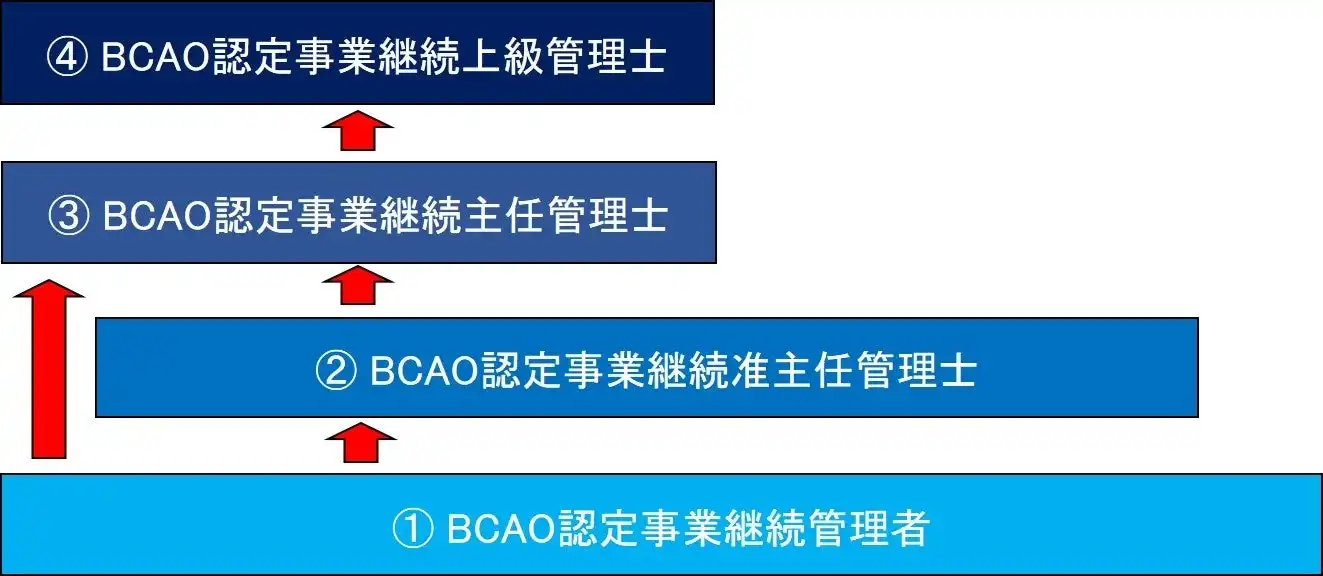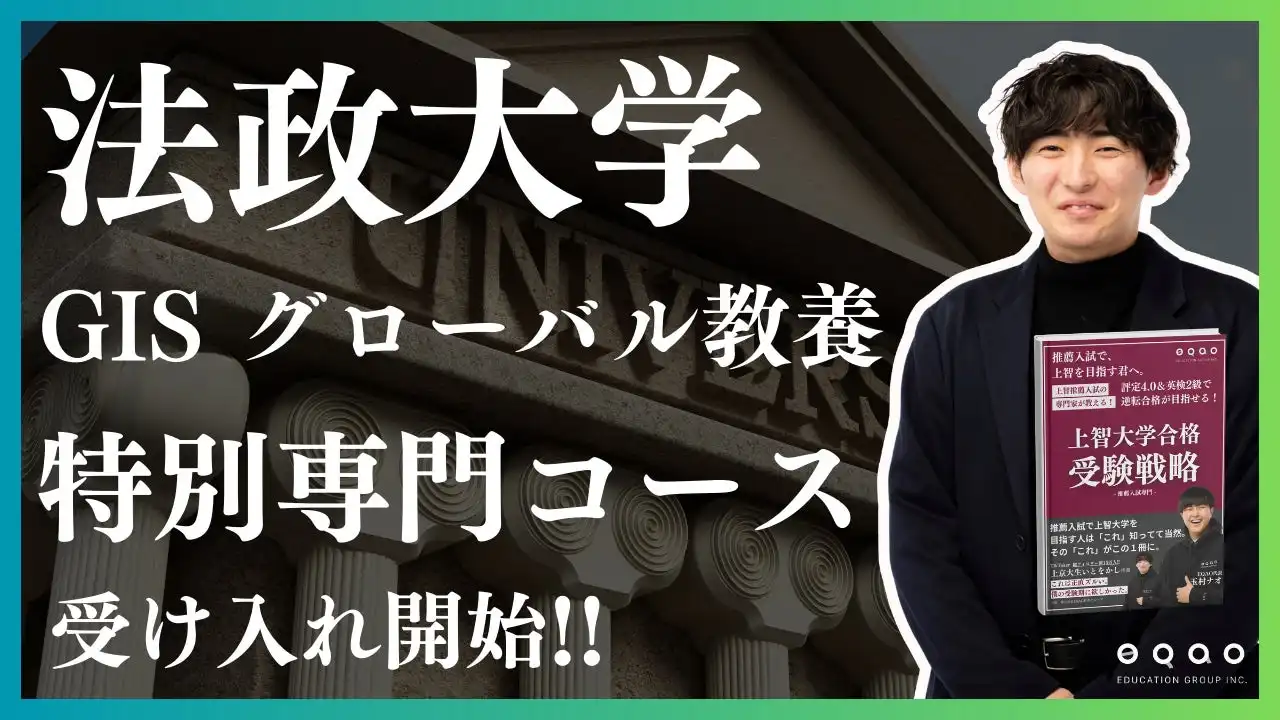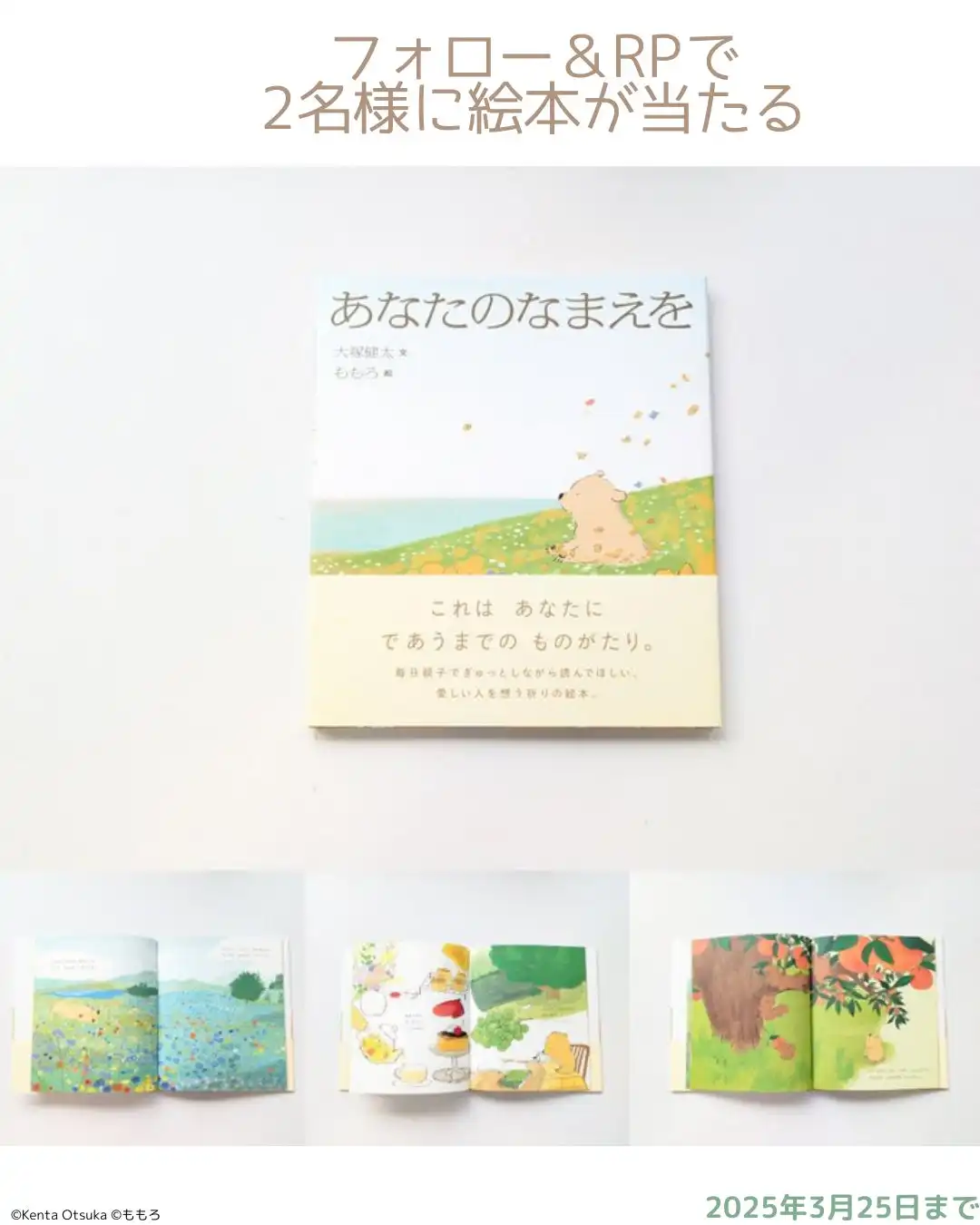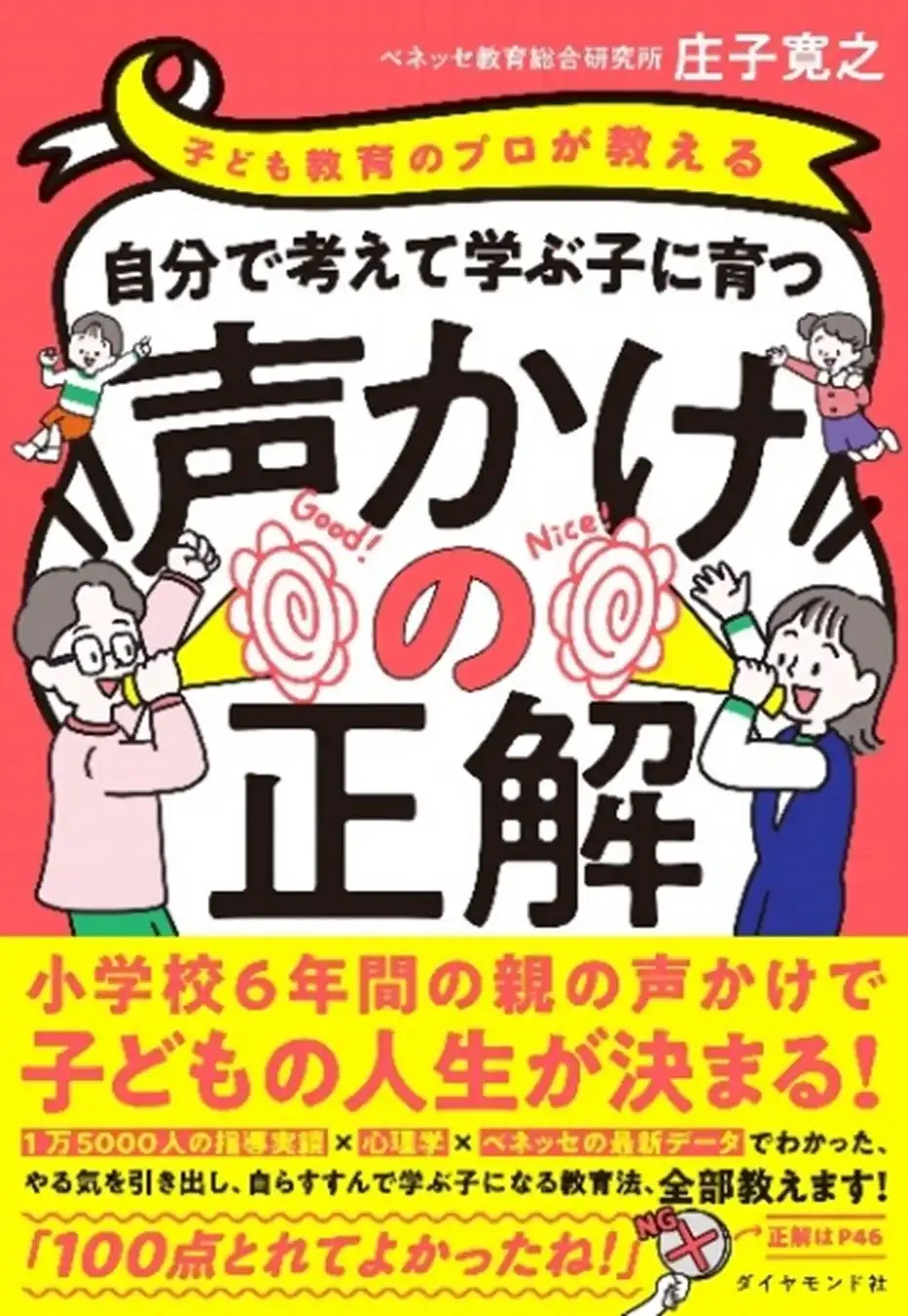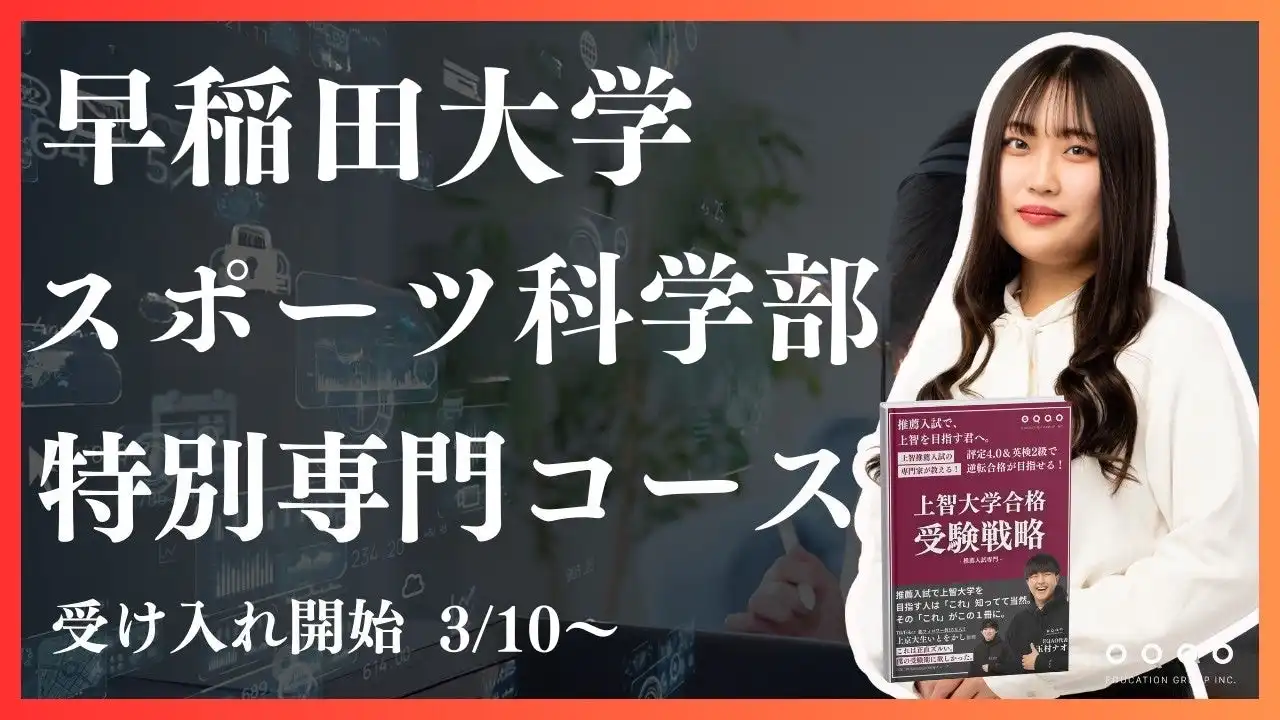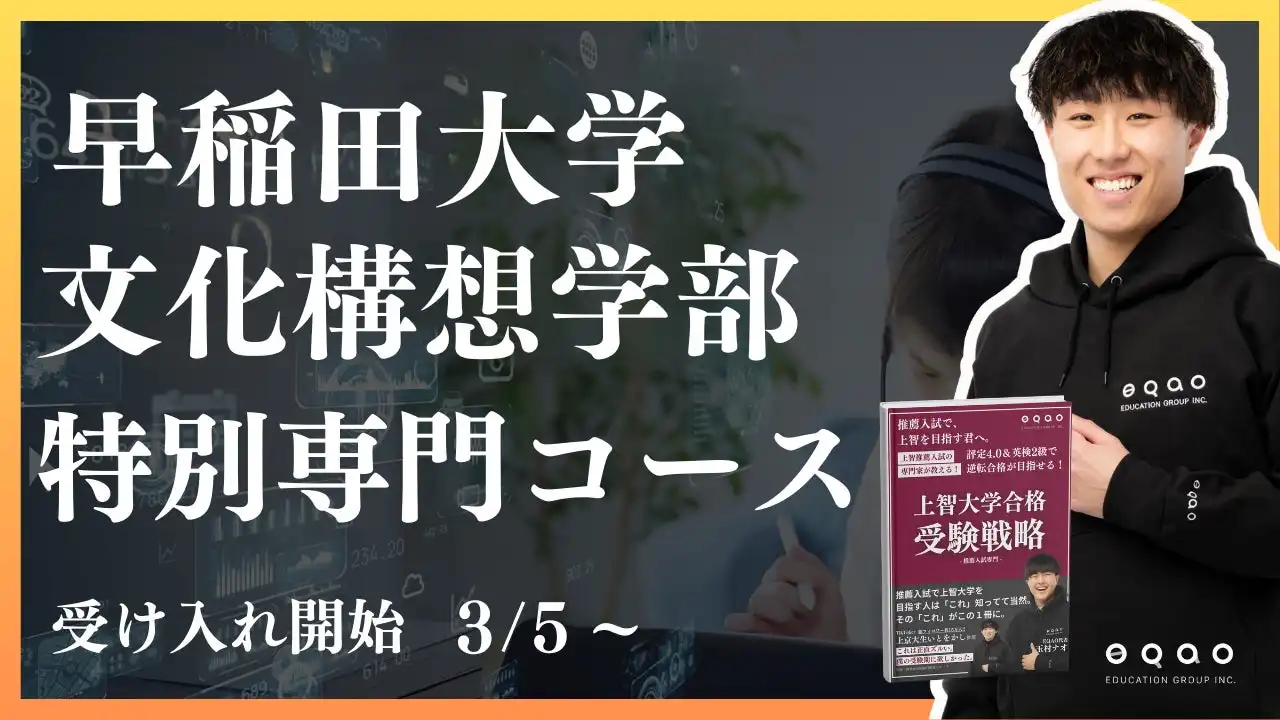高校生が探求テーマを決めるときの選び方と具体例を解説
高校生の探求テーマを選ぶための決め方・具体例
- 【解説する内容】
- 探求テーマの決定プロセスと選び方のポイント
- 研究分野ごとの具体的な探求テーマ例
探求テーマの決定プロセスと選び方のポイント
探求テーマを選ぶ際は身近な疑問や問題意識から着手することで、研究への意欲を持続的に維持することができます。日常生活で気になった現象や地域社会の課題など、自分自身が強い関心を持てるテーマを選択することで、より深い探求活動が実現できるでしょう。
探求活動では研究の独自性と実現可能性のバランスを考慮することが重要となります。学校の設備や実験機材、調査に必要な時間や費用などの制約を踏まえた上で、新しい視点や切り口を見出すことで魅力的な研究テーマを設定できます。
研究テーマを決める際は、以下のポイントを意識しながら検討を進めていくことをおすすめします。学術的な価値と実現可能性の両立を目指しましょう。
- 【ポイント】
- 自分の興味関心との一致度を確認
- 研究の実現可能性を評価
- 先行研究との差別化を意識
- 社会的意義や波及効果を考慮
- 研究期間との整合性を確認
探求テーマの設定では指導教員や専門家からのアドバイスを積極的に取り入れることも効果的です。研究の方向性や実験方法について、経験豊富な視点からの助言を得ることで、より充実した探求活動を展開できます。
探求活動を通じて得られる成果は、進路選択や大学入試にも活用できる重要な材料となります。テーマ選びの段階から将来の目標や志望分野との関連性を意識することで、より意義のある研究活動が実現できるでしょう。
研究分野ごとの具体的な探求テーマ例
探求活動では理科や社会科などの教科に関連するテーマだけでなく、SDGsやプログラミング、地域活性化など幅広い分野から選択することができます。Google Colaboratoryを活用したデータ分析や、環境DNAを用いた生態調査など、最新の技術や手法を取り入れた研究も増加しています。
研究テーマの選定では文理の枠を超えた学際的なアプローチも重要となります。ArcGISを使用した地理情報システムの活用や、RやPythonによる統計解析など、複数の分野を横断した新しい視点からの研究が注目を集めています。
各研究分野における代表的なテーマ例を以下の表にまとめました。具体的な研究事例を参考に、自分らしいテーマを見つけていきましょう。
| 【研究分野】 | 探求テーマ例 |
|---|---|
| 自然科学 | 微生物による水質浄化の研究 |
| 社会科学 | 地域観光資源の活用方法 |
| 情報技術 | AIを活用した農作物の品質評価 |
| 環境科学 | バイオマス発電の効率化研究 |
| 人文科学 | 伝統工芸の継承と革新 |
探求テーマの決定後は、研究計画書の作成や実験方法の検討など具体的な準備作業に移行していきます。研究の進め方や必要な機材、調査対象など詳細な実施計画を立てることで、スムーズな探求活動の展開が期待できます。
探求活動の成果は論文やプレゼンテーションの形でまとめることになります。研究過程での気づきや発見を丁寧に記録し、論理的な考察を加えることで、説得力のある研究成果を導き出すことができるでしょう。